英語と日本語がクロスオーバーする、ボーダレスで独特のサウンドが特徴的なRyu Matsuyama。新作アルバムでも、特有のメロディーと多幸感あるサウンドが心に響く内容となっている。今作ではシンガーソングライターの優河やラッパーのBIM、そしてmabanua、関口シンゴ、Shingo SuzukiのOvallの3人という豪華アーティストとコラボし、ジャズやヒップホップ、ポップスなど、さまざまな音楽ジャンルを超えたボーダレスで、新たなるサウンドスケープを提案。まさに至高の一枚に仕上がっている。今回は、Ryu Matsuyamaのメンバー3人に、アルバム『from here to there』の制作に関する話を中心に、彼らの音楽的インスピレーションの元、今後の展望などについて聞いた。
──最新アルバムのタイトル『from here to there』の由来を教えてください。
Ryu「このタイトルは、漠然とした"何か"にしたいという思いから、出来るだけ明確なメッセージ性を与えないタイトルにしたかったんです。『from here to there』というタイトルを見た時に、それが過去から未来なのか、過去から現在なのか、それとも場所を意味するのか、想像してもらえたらと思ったんです」
──アルバム全体を通して聞くと、なんとなくそのタイトルの感じ、イメージを受けました。曲はどのように制作されるのでしょうか?Ryuさんが一旦デモ音源を作られてから、3人で編曲していく流れですか?
Ryu「メンバーであまり話すことはありません。仲が悪いとかではないのですが(笑)、そのやり方で約10年やってきたので。ただ最近、このコロナ禍になってからは特にデータのやりとりが中心になっていて、デモ音源のプロジェクトファイルをメンバーに送って、それが戻ってきた時に“なるほど!こーいうアプローチか!”となることが多いです。言葉ではなく音楽の上で、メッセージの様なやりとりを3人でやっています」
──そこは3人で長くやってきたからこそのリレーションシップという感じなのでしょうね。
Jackson「なんとなくの塩梅が分かっているということなんだと思います。自分を出しすぎるとバランスが悪くなるということを、3人とも分かっているんですよ」

──バンドを組まれて、現在の3人体制でやり始めてからは何年目ですか?
Ryu「3人では8年くらい。僕とTsuruちゃんでRyu Matsuyamaというバンドとしてやりはじめたのが、約10年目になります」
──Ryu Matsuyamaは、イタリアで結成したわけではないんですね。
Ryu「そのタイミングでも音楽はやっていましたが、イタリア時代に組んでいた別のバンドが解散して、日本に来てからは“ソロでやりたい”という気持ちがあったので、自分の活動を始めたという感じです。それが2010年ですね」
Tsuru「「“イタリアで結成!”ということにした方がよかったかな(笑)」
Ryu「そっちの方が格好よかったかもね(笑)」
Jackson「マネスキンにも呼ばれたかもしれないね(笑)」
──今回、フィーチャーしたアーティスト、mabanuaさん、関口シンゴさん、Shingo Suzukiさん、BIMさん、優河さんとの関係は?
Ryu「mabanuaさんとは、前作『Borderland』のプロデュースをしていただいて、その後のEPの収録曲「Under the Sea feat. Max Jenmana」は関口シンゴさんにお願いしたという流れがあったんです。Ovallは、僕ら3人とも大好きですので、Ovallの全員とやってみたいという気持ちも強かったので、今回、ついにShingo Suzukiさんにもお声がけさせていただき、「hands」の編曲をお願いしました」
──シンガーソングライターの優河さんとは?
Ryu「優河ちゃんは、そもそもTsuruちゃんの専門学校時代の同級生だったんですよ」
Tsuru「昔から対バンとかで会う機会も多くて、イベントが一緒の時はライブも一緒にやったりしていました」
Ryu「そうですね、10年くらい前から一緒にライブをやったりしていたし、あの唯一無二な声とついにコラボすることができたという感じで、本当に嬉しかったです」
──ラッパーのBIMさんとは?
Ryu「BIMくんは、前作EPでDaichi Yamamotoくんとやってから“またラッパーとコラボしたい”という気持ちがあって、THE OTOGIBANASHI'Sも聞いていましたし、彼のラップがすごく好きだったんですよ。今回の曲で、早いラップで、フロウもカッコイイのはBIMくんしかいないと思ってお願いしたら、OKしていただきました」
──もともと面識はあったのですか?
Ryu「実はまったくなかったんです(笑)。“大好き”というだけで依頼させていただきました」
──“好きだからお願いしたい”という仕事の仕方はいいですね。
Ryu「実は、Daichi Yamamotoくんもそうで、彼の名前は知っていましたが、候補に上がっていたラッパーの中で声がピカイチだったんですよ。それで第一印象から“この人!”という感じでお願いして、今回もそういう感じでやらせていただきました」
──アルバムを制作するにあたって、心がけていたことはありますか?
Ryu「今回は、バタバタだったような気がします。もちろん過去に作っていた曲で、ずっと候補にあった曲もピックアップしているのですが。例えば、「all at home」はかなり初期に書いた曲ですし、いろいろと選んで、そこから詰めて、という感じで制作しました。何かを意識して作ろうというよりかは、“アルバムに向けて、頑張ろう”という感じでしたね。あとは、“全体の流れをどうする?”とか、“どういう曲を入れたらバランスがいいか?”という考え方で動いていました」
──英語と日本語、両方を織り交ぜた歌い方をされていますが、その使い分けの考え方を教えてください。
Ryu「以前から、日本語と英語のバランスをどこかでとりたいと模索していたんです。初期の「Taiyo」という曲のように、日本語を入れた方がよく聞こえるみたいな、そういうバランスを考えて書いていますね。もともと僕は日本に住んでいなかったし、日本語で育っていないこともあり、約10年活動して、ようやく日本語だけの曲も作れるようになったんです。だから、日本語の歌詞の割合も増やしていきたい気持ちはありました。ただ英語の曲も大事にしながら、そのバランスをうまくブレンドさせて、“どちらでもない”というか、“どっちにも聞こえて欲しい”というスタイルですかね。いままで100%日本語という曲がありませんでしたから、“みなさんにも聞いて欲しい”という気持ちを今回、ようやく実現できたと思っています」
──2017年リリースのアルバム『Leave, slowly』は、すべて英語歌詞でしたね。
Ryu「その時代はすべて英語歌詞でした。その後から、ソロ活動でも日本語と英語をどうブレンドしたら、日本語が英語に聞こえて、英語も日本語に聞こえる…そのバランスを模索しました。僕的にようやく良い感じのブレンド感が出来たと思えたのが、前作『Borderland』でmabanuaさんと初めて共作した「Blackout」なんです。それを今回もっとその先にいってみたいと思って、「blue blur」が完成しました。だから経験ですよね」
──今作で苦労された点は?
Tsuru「個人的には「hands」のベースですね。編曲プロデュースしてくれたShingo Suzukiさんにベースの細かい指示をいただいたのですが、いいテイクとれるまでに時間かかっちゃって(笑)でも改めて勉強になりましたね」
Jackson「ベースのニュアンスが違うんですよね」
Ryu「ニュアンスって、それぞれありますし、ベーシスト同士というのもあったと思います」
Jackson「ドラムに関しては、このコロナ禍になって、データだけでやりとりするようになり、彼らが入れてきたドラム音に出来るだけ近づけるという作業が多くなった点ですね。僕が入った8年くらい前は、Ryuくんが持ってきたデモ音源に対して、3人でセッションして味付けしていったのですが、最近は、なるべくデモのドラムサウンドに近い感じで、原曲のイメージを壊さないようにドラムをつけるという、僕にとっては慣れていない作業で大変でした」
Ryu「デジタルの打ち込みは自由なので、ドラマーの腕の数を考えなくていいんですよ」
Jackson「だから、すごい量のドラム音が送られてきて、これは腕2本じゃ足りないなって(笑)」
──例えば、すべてを合わせた時に、思ってもいなかった化学反応が生まれたみたいな曲はありますか?
Ryu「僕は、関口シンゴさんが編曲プロデュースしてくれた「snow」という曲ですね。ダークで静かな曲として作って、ピアノと声だけで送ったのですが、戻って来た音が新しかった。もちろん、僕らも“シンゴさんのテイストをいっぱい入れてください!”というお願いをしていたのですが、真反対のものを作られてきたので、“すごいな!”と思いましたね」
Jackson「僕は「kid」ですね。これはRyuくんのソロ曲なのでまだバンドではやったことがない曲なんです。これまで、Ryuくんは覚えてないかもだけど、ドラムとベース、キーボードのバンドスタイルで必ず曲をやりたいという思いがあったので、だからソロの曲をライブのセットリストやアルバムには入れてこなかったんです。それを優河ちゃんというベストなシンガーソングライターが決まったこともあって、“ピアノだけでいいかな?”って。いさぎよく“ピアノと歌でいこう”となった時に、バンドが成長したなと思いましたね。そういう良い曲に対して“バンドでなくてもいい”というチョイスが出来るようになったというのが、僕的には驚きました」
──それは“化学反応が生まれた!”みたいな感じですね。
Jackson「僕的にはドラムのパートがないので、“休める”という感じですが(笑)」
Ryu「そういうことを言うから“バンドでやろう”って言ってるんだよ(笑)!」

──全体的にアップテンポではなく、ミドルな感じで、“癒し”ではないですが、そういう雰囲気を感じましたが、何かしらの影響があったのでしょうか?
Ryu「たぶん歳をとったのかなと(笑)」
Jackson「もともとアップテンポな曲は少ないです」
Tsuru「勢いはないですね(笑)」
Ryu「ないわけではないのですが、意識的に早い曲を書こうとしないと書けないというのがあります。いまは、本当に書きたいものを書いているというよりは、出てきたものをアレンジしてるんですね。Tsuruちゃんのアレンジも面白くて、僕にはない考え方ですし、いろんな人のアイディアが入ってくることによって幅が広がるというのは、mabanuaさんが参加した時に分かったので、経験といままでの積み重ねが反映されていると思います」
──「reckless child」は、今回のアルバムのなかではアップテンポな感じですよね。
Tsuru「これが最初で最後かもしれません(笑)」
Ryu「でも、みんなの方向性がだんだん定まってきたというか、なんとなくRyu Matsuyamaの音像がエンジニアの西川(陽介)さんとともに出来上がってきているんですよ。以前は“こういう人たちに憧れている!”みたいな部分が出ていたのですが、いまはゆるやかに自分たちの音像というか、ジャンルをやる方向になってきていると思います」
──今作において、リスナーにこういう感じで聞いて欲しいとか、こういう状況で聞いて欲しいみたいな希望はありますか?
Ryu「この『from here to there』というタイトルは、思想的に根本にあるのは宇宙旅行者なんですね。『And look back』でもそうでしたが、宇宙旅行している宇宙飛行士が過去を振り返ったり、未来を見ていたり、そういうストーリーを描いているんです。だから、移動中に聞いて欲しいというのはありますね。車の中もそうですが、僕は電車が好きなので、電車に乗って、ぼーっと考えごとをしながら聞いてもらえたら、その景色に溶け込んでくれるかな」
Tsuru「それ、僕も同じです!僕は引きこもりなので出勤しないのですが、最近は電車にも乗ってなくて(笑)。でも、時々乗る機会があって、“辛い!”と思いながら電車に乗っているじゃないですか。その時に聞く音楽って、家で聞くのとはまたちょっと違っていて、格段に良いんですよ。月曜日の朝に、“無理だな”と思っている時に聞いてもらったら、“今日、頑張ろうかな”とか思ってもらえる気がする」
Ryu「特に1曲めの「satellite」というのは…」
──ピアノのインスト曲ですね。
Ryu「僕らは、インストで物語が始まるというアルバム構成にしているのですが、この曲は、イヤホンのノイズキャンセルをオフにして、電車の発車するベルだったり、人の雑多な音が混ざった上で聞いて欲しいんですよね。そういう状況で聞くことで出来上がる構想で書いた曲なので。そこからノイズキャンセルをオンにしてもらって、曲に入って、ストーリーに入っていくと、より一層楽しめると思います。だから、ぜひこの一曲だけでもいいので、電車の中とか、移動している時に聞いてもらえたら嬉しいですね」
──「satellite」は、曲がスタートしてもなかなか音が始まらないですよね。
Ryu「実は薄っすらと僕らが機材を片付けている音を入れています。最初は駅での音とかのノイズを入れようと思ったのですが、それって自分でコントロール出来ますから。だから、自分の中でストーリーをはじめてくれれば嬉しいという気持ちで作りました。それが一番良いかなと思います」
Tsuru「でも、あの曲は、“今日も頑張ろう”と思うのか、“今日は休もう”と思うのか、どっちか分からないよね(笑)」
Ryu「それでもストーリーが始まるからね。僕は面白いなと思います」
Jackson「前の時代って、部屋にオーディオがあって、正座して音楽を聞いていたじゃないですか。このアルバムは、“さあ、Ryu Matsuyamaを聞くぞ!”ではなく、生活の中で自然に聞いてもらえるのが一番嬉しいですね」

──音楽を作ったり、演奏される上で、何にインスピレーションを受けますか?
Ryu「以前は映画を観ることでしたが、いまは観なくなってしまいました。最近、移動中もそうですが、出来るだけ外の景色を見るのがいいと気づきましたね。たまに電車の中でもケータイを見ない日をつくったりして、むしろケータイを置いていくくらいのレベルで散歩したり。すごく大事なことなんですけれど、最近は出来ていなかったと自分でも改めて気づいたんです。便利になった生活の中で、目の前にある美しいものをできるだけ見るようにしようと心がけて、それを歌詞に落としこみたい。特に「kid」や「reckless child」、「hands」もそうですけれど、このコロナ禍で散歩しながら感じたものを落とし込んでいます。だから、最近は景色を大事に見るようにしています。あと、娘が生まれたこともあって、娘と散歩しながら気づくものもあったりしますね。僕にとって娘の概念が面白すぎなんですよ。それを見ているのが僕のインスピレーションになっています」
Tsuru「僕は、なるべくスピーカーで音楽を聞くようにしています。それは特定の誰かの曲ではなく、例えば、Apple Musicの最近追加された洋楽R&Bみたいな、そういうのを適当に流す。テレビの音とか、いろんな音が鳴っている中で、スピーカーで流しながら仕事したり、普通に生活していると、耳が反応する音楽があったりするんですよね。そういう音楽にインスピレーションを受けています。あとは、映画とゲーム…8割がたゲームです(笑)」
──どういうゲームをやられているのですか?
Jackson「このふたり、ここから2時間くらいは話しますよ(笑)」
Ryu「僕らはPS4です」
Tsuru「たまたまもらってから沼ってますね(笑)。プレステをやる時間をつくるために頑張るみたいな」
Ryu「『Dead by Daylight』というゲームで、Tsuruちゃんとオンラインでやっているのですが、結構チャット機能で話せるんですよ。それで大阪のレーベル担当の人とつながって、そこから“京都のディレクターさんを紹介しますよ!”とか、ミュージシャンともつながったりして、どんどん輪が広がっているんです。それっていい時代だなと思いましたね」
Tsuru「リアルの友達より、オンラインの方が多いかもしれないです(笑)。でも、流石にゲームからはインスピレーションはもらっていないですね」
──ある意味、何かは得ていますよね。
Tsuru「それなら胸張って“ゲームやってます!”って言えますね(笑)」
Jackson「僕は、ジャズがすごく好きで、月に2、3回、ブルーノートとか、コットンクラブとかにライブに行っています。先日、ザ・ルーツ(The Roots)のライブに行ったのですが、海外のレジェンドのスーパードラマーとかのドラムの叩き方を見ると、考え方も全然違いますからね。例えば、クエストラブなんかは、余計なことを一切しない。僕はライブをやり始めた頃は、“いかに自分が目立つか?”とかしか考えていませんでしたから。でも、お客さんを喜ばせるために弾かない、叩かないという、引き算した方が見た目としてカッコイイバンドになったりする。それって人のプレイを見て、目の当たりにしないと学べないですから。いろんな上手な人の演奏を見て、時には10代とか、20代とかも見て、影響を受けて生かしていますね。あとは美術館。“そもそもなぜ音楽をやるのか?”ということをアートから感じたりしています」
Tsuru「ストイックだよね」
Jackson「他の人の作品を見て、“なぜドラムを叩くのか?”とかをなんとなく考えるのが好きなんですよ。最終的な話ですが、自分のやっていることが、音楽以外でもお客さんに伝えられたらいいですよね」
──今後の展望を教えてください。
Ryu「このコロナ禍で、やはり展望が見えなくなったということもあって、とりあえず、作品に残そうと。2020年4月29日に『Borderland』をリリースした時は、緊急事態宣言でお店が全部閉まってしまった状況だったんです。だから、僕らがやりたいことを、一瞬一瞬、その時に出来ることを刻んでいかないと自分が残せていけないなと。一期一会ですよね。結局、“なぜ音楽をやっているか?”といえば、自分が言いたい言葉、伝えたい詞、やりたい風景があるからなんです。それを作品として残すことでみんなに聞いてもらいたい。もちろんライブもやりたいですが、たくさんの音たちをみなさんに届けたいというのが今後の展望ですね。とにかく、このコロナで漠然としすぎて、いろいろと難しくなってしまったと感じています。コロナ前だったら“海外に行きたい!”とか、簡単に言えたかもしれないですが。だから、とりあえず作品を沢山つくって、いまやれることを全部残していきたいですね」
Tsuru「僕は、Zeppでワンマンツアーしたいです。そして、日比谷の野音でワンマンが出来るくらいのバンドにしたい。ブイブイ言わせられるような。それが展望です(笑)」
Jackson「展望というか、先日、テレビ番組に出たのですが、そういう大きなメディアに出てもいいんじゃないかなと。いままで、別に出たくなかったわけではないのですが、そろそろ出てもいいんじゃないかなと(笑)」
Ryu「野望だよね(笑)」
Jackson「あとはラジオ番組をやりたいです!」
──ありがとうございました!

(おわり)
取材・文/カネコヒデシ
RELEASE INFORMATION

Ryu Matsuyama『from here to there』
2022年9月28日(水)発売
VPCP-86422/3,000円(税込)
バップ
LIVE INFORMATION

Ryu Matsuyama presents “to get there”
Ryu Matsuyama(Solo)
10月15日(土) 大阪 雲州堂 w/小野雄大
10月16日(日) 名古屋 K・D ハポン w/小野雄大
10月23日(日) 福岡 LIVLABO w/優河
11月10日(木) 札幌 円山夜想 w/優河
Ryu Matsuyama(band)
12月14日(水) 東京 キネマ倶楽部 w/coming soon
12月21日(水) 大阪 心斎橋 Music Club JANUS w/coming soon
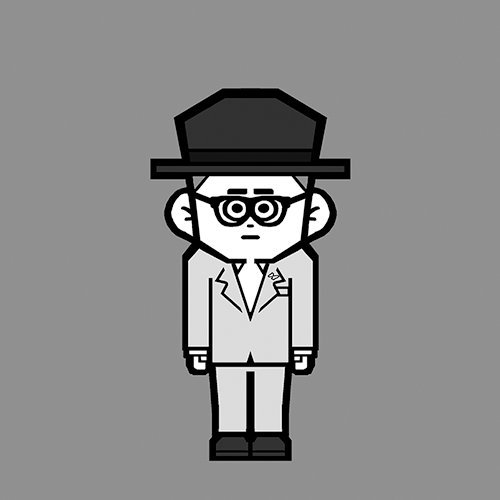
カネコヒデシ
メディアディレクター、エディター&ライター、ジャーナリスト、DJ。編集プロダクション「BonVoyage」主宰。WEBマガジン「TYO magazine」編集長&発行人。ニッポンのいい音楽を紹介するプロジェクト「Japanese Soul」主宰。そのほか、紙&ネットをふくめるさまざまな媒体での編集やライター、音楽を中心とするイベント企画、アパレルブランドのコンサルタント&アドバイザー、モノづくり、ラジオ番組製作&司会、イベントなどの司会、選曲、クラブやバー、カフェなどでのDJなどなど、活動は多岐にわたる。さまざまなメディアを使用した楽しいモノゴトを提案中。バーチャルとリアル、あらゆるメディアを縦横無尽に掛けめぐる仕掛人。
こちらもおすすめ!
-

大原櫻子 billboard classics インタビュー――大原櫻子×オーケストラ=新たな可能性が花開く、未来へのステージの予感
encoreオリジナル -

笹川美和『スピカ』インタビュー――プラネタリウム・ライヴ"LIVE in the DARK"から生まれた星空の曲たち
encoreオリジナル -

ORANGE RANGE『Double Circle』インタビュー――約4年ぶりとなるオリジナルフルアルバムをリリース!そして全国ツアーへ!!
encoreオリジナル -

Novel Core『No Pressure』インタビュー――プレッシャーを受け入れて前に進んでいく
encoreオリジナル -

Salyuインタビュー――公演間近! "salyu × salyu" 3人のヴォーカリストによるシュティムング"
encoreオリジナル -

GLIM SPANKY『Into The Time Hole』インタビュー――心の中のナイフで切り裂いて
encoreオリジナル




