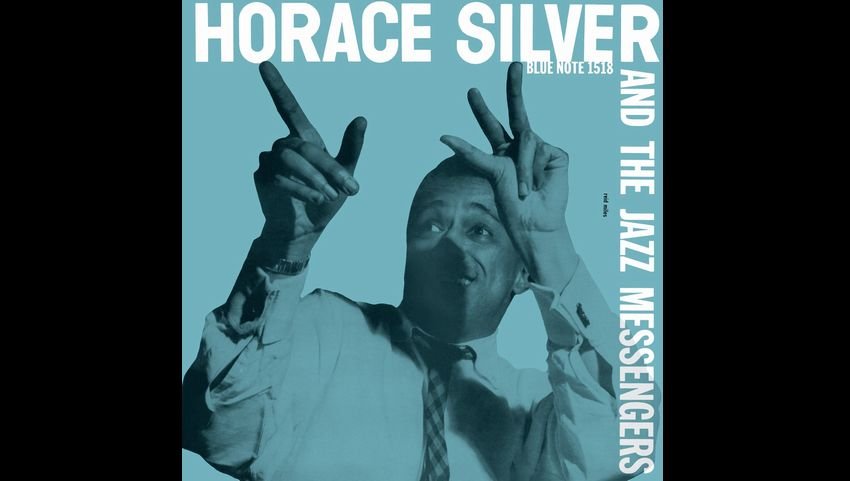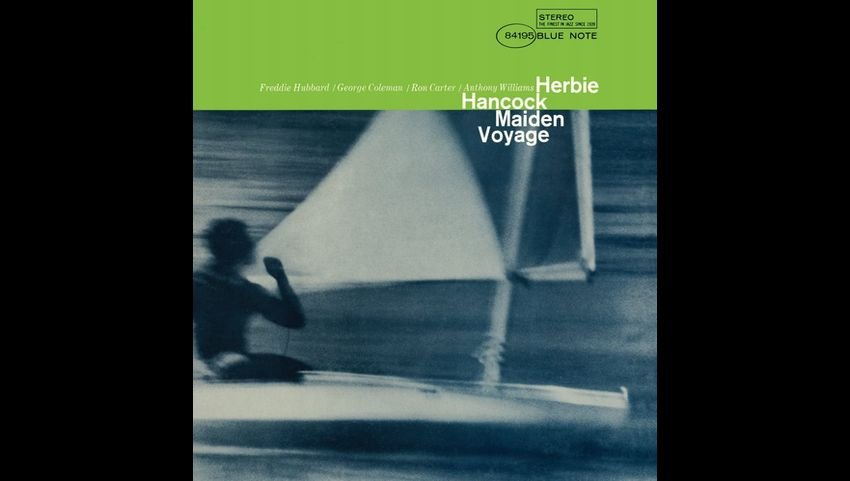かつて“クール・テナーの巨人”と呼ばれたスタン・ゲッツも、それこそクール・ジャズ全盛の40年代末から、晩年90年代に至る活動期間を眺めると、“クール”な演奏をしていたのは初期の数年に過ぎない。つまり、60年も昔の、スタン・ゲッツが最初に人気を博した時代のキャッチフレーズが彼のイメージを限定している傾向がある。今回はそうした偏りを払拭し、スタン・ゲッツの全体像を幅広く知っていただくため、録音年代順にジャズ喫茶でもよくかかる傑作アルバムを並べてみた。
最初のアルバム『スタン・ゲッツ・カルテット』(Prestige)はまさにゲッツ、クール時代の名演で、テナーの音色、演奏の表情を淡々とクールに抑えながらも、ソロの切れ味は抜群。ちょっと聴きには地味な印象だが、聴けば聴くほどゲッツの実力が知れる初期の傑作。
それから2年後、52年録音の『スタン・ゲッツ・プレイズ』(Verve)では、早くもクールなサウンドは影を潜め、むしろ心温まるウォームなテナーに変身している。それでも同時代の黒人テナー奏者、ソニー・ロリンズなどに比べれば、相対的に軽やかな白人ジャズの特徴は明らか。
55年録音の『ウエスト・コースト・ジャズ』(Verve)になると、トランペットのコンテ・カンドリ、ドラムスのシェリー・マンなど、軽やかさが身上の“ウエスト・コースト・ジャズ”のスターたちと共演したアルバムだが、ゲッツのサウンドはむしろハードで、東海岸のハードバッパーとさして変わらない力強い演奏になっている。
そうしたゲッツのパワーを証明するのがディジー・ガレスピー、ソニー・スティットと共演した『フォー・ミュージシャンズ・オンリー』(Verve)で、バップ・トランペッター、ガレスピー、アルトの名手スティットといった、黒人第一線ジャズマンと互角に渡り合って一歩も引けをとっていない。このあたりになると、一体どこがクールなんだと言いたくなる、熱いゲッツが聴ける。
ヴァーヴ・レーベルは大物同士の顔合わせが多いが、トロンボーンの名手、J.J.ジョンソンとの一騎打ち(ちょっと大ゲサ)を記録したのが『スタン・ゲッツ・アンド・J.J.ジョンソン・アット・ジ・オペラ・ハウス』(Verve)だ。すべてに大らかなヴァーヴ・レーベルらしく、録音データが二転三転してマニアを悩ませたが、演奏は第一級。
ところで、ゲッツ人気には山場が何度かあって、クール時代がその最初だとすれば、2度目は60年代のボサ・ノヴァ・ブームだろう。ボサ・ノヴァ界の大物、ジョアン・ジルベルトと共演した『ゲッツ・ジルベルト』(Verve)は空前のヒットとなり、再びゲッツは“時の人”となった。ボサ・ノヴァ特有の気だるい気分とゲッツの余裕に満ちたテナー・サウンドがうまい具合にブレンドしたのだ。
その流れを受けた『スイート・レイン』(Verve)はゲッツ60年代の名盤であると同時に、サイドマンとしてデビューしたチック・コリアの人気も高めた。躍動感に満ちたチックのピアノと、ダイナミックな力強さを秘めたゲッツのテナーが緊密に噛み合った名盤だ。
世間的にはフュージョンという見方があるらしいが、80年代の『アパッショナード』(A&M)は、そうしたジャンル区分があまり意味を持たない傑作である。要するにバックサウンドが何であれ、ゲッツのサックスにはオリジナリティと強烈な表現力があるのだ。そして最晩年の『ピープル・タイム』(EmArcy)の真に迫った切実さを聴くと、いまさらのようにゲッツの偉大さが見えてくる。死を直前にした《ファースト・ソング》はゲッツ畢生の名演といって良い。
文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」
東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。