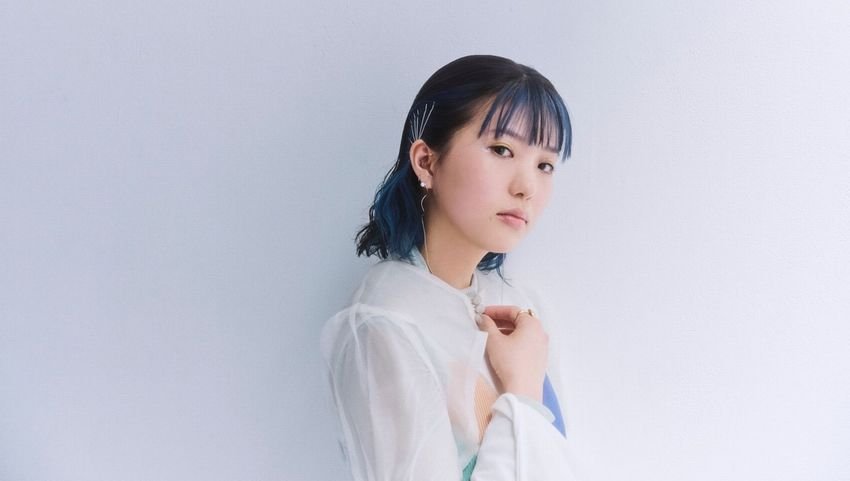INTRODUCTION
2013年UK発祥の本家「LOVE SUPREME」は、ジャズのみならず、ファンク、ソウルまであらゆるジャンルを横断する音楽フェスだ。その日本版たる「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」は、2020年、2021年とコロナ禍でリスケを余儀なくされたのだが、新しい時代のジャズはリスナーに浸透し、楽しくもユニークな接合を果たしていたというのが、同フェス2日目を見終えての実感だ。
WONKのキーボーディストである江﨑文武とAnswer to Rememberの石若 駿の対談――「グラスパー以外全員友達」という見出しが興味深い――を引くまでもなく、自身のバンド以外での共演、客演、時に作曲、編曲者としても活躍するミュージシャンたちが、複数のステージでホストバンドであり、ゲストでもあるというジャズフェス特有の交流はこのイベントにおいても同様で、演奏でコミュニケーションするという、まさにジャズの醍醐味を体感することができた。
会場となった秩父ミューズパークは西武秩父駅にほど近い長尾根丘陵にある。公園内の野外音楽堂を使ったTHEATRE STAGE、芝生エリアに特設されたGREEN STAGEというふたつのステージに加えてアクセスフリーなエリアにはDJテントも設けられた。各ステージのアクトはすべて50分前後とたっぷり時間がとられ、かつフードトラックやテントを横目にステージ間を移動すればすべてのアクトを見ることも不可能ではないスロットが組まれており、全アクトを制覇した来場者もいるのではないだろうか。

WONK
さて、ここからはいくつかライブを紹介していこう。2日目のトップバッターはWONK。ある意味、この日の出演者に何らかの関係がある要の存在だ。もちろん、それは他のバンドの立場からも言えることではある。合宿形態での制作で、演奏者の生の音にフォーカスした新作『artless』がリリースされたばかりとあって、ごくごく自然な導入でアルバム1曲目に収められた「Cooking」からスタート。長塚健斗(Vo)が「まだ体が起きていないかもしれないですけど、ここからちょっとずつギアを上げていければ」と、この日の開幕を同時に告げているようだった。サポートのMELRAW(Sax/Fl)と小川 翔(Gt)は昨日、kiki vivi lilyのサポートも務め、MELRAWはこの後、Answer to Rememberにも参加するという、キーマンでもあった。オーガニックなグルーヴは踊るというより、ストレッチやヨガがしたくなる感じ。続く「Orange Mug」もグッと生音のアレンジに。MELRAWのサックスソロには大きな拍手が起き、ステージ上に描かれたピープルツリーをよく知るオーディエンスが集まっていることがうかがい知れた。
曇り空に時々日が射すこの日のコンディションに、井上 幹(Ba/Gt)が弾くアコギが最高に心地よい「Migratory Bird」。タイムテーブルが決まった当初、WONKが昼間のトップバッターとは意外だと感じたが、『artless』の世界観は明るい野外のシチュエーションに似合うし、フェスでじっくり音楽を心身に染み込ませることのなんと贅沢なことか。このスロットは大正解だ。そこに石若 駿がオンステージ。長塚が「ドラムがもうワンセットあるからね」と、察しのいいファンと無言の会話を交わす感じが好ましい。石若参加曲と言えば1stアルバム『Sphere』収録の「Real Love」である。ラッパーのJuaも参加し、今日1日のすべてのアクトでいったいどれだけミュージシャンの往来があるのだろう?とワクワクする。荒田 洸(Dr)と石若の抜き差しが絶妙なツインドラムで大いに沸かせる。演奏を終えグータッチする2人に大きな拍手が贈られる。江﨑のオルガン的な鍵盤の不思議なサウンドや井上のイマジネーションに富むベースソロが特徴的で、一気にディープな世界観へいざなう「Butterflies」へと、アルバムの世界観に戻ってくる。
「こうやってフェスが戻ってきてくれて嬉しい。今日この後もすごい人ばかりだから!」と、一人の音楽ファンとしても喜びを溢れさせる長塚にオーディエンスもまさに!とばかりに拍手で返す。晴れて風も吹き始めたシチュエーションにハマる「savior」、「強がってばかりじゃ生きていけない、弱いところも出して許し合って行けたらという曲を書きました」という曲振りからオフビート抜けのよいお得意のネオソウル「Euphoria」ですっかりオーディエンスをリラックスさせた後、結果的に彼らにとって初の日本語詞曲となる「Umbrella」を披露。歌詞にある<鉄の雨に打たれ 倒れ逝く人々>が現実に存在する今の世界。一言一言に祈りを込めているのは長塚の歌だけではなく、プレイすべてに慈しみが横溢していた。野外フェスの選曲の概念を塗り替える、素晴らしい時間を共有できた。

Aile The Shota、Answer to Remember、Nulbarich
続いては、GREEN STAGEの1番手、Aile The Shota。デビュー4ヵ月にしてリリースしたばかりの「IMA」が各種サブスクR&Bチャートで上位を獲得した注目株だ。初日に登場したSKY-HIは、日本版ラブシュプのユニークネスだが、SKY-HIが主宰するレーベル「BMSG」の一角を担うAile The Shotaもまたユニークな存在だろう。シティポップが絶妙にリンクしたイメージに、洗練され、かつ親しみやすさを併せ持つ楽曲に透明感のあるボーカルが映える。デビュー曲の「AURORA TOKIO」などで場を温めつつも「一人だと持て余しちゃうので」と、Nenashiを呼び込んでの「Like This」、そしてレーベルのボスでもあるSKY-HIとの「me time -remix-」を対照的なボーカル/ラップスタイルで聴かせてくれた。
デビュー4ヵ月、この場所にいることそのものが光栄だし、嬉しくて仕方がないと、丁寧に伝えるスタンスも新鮮だ。GREEN STAGEに現在ヒット中の「IMA」のトラックが流れ出すと、80sのエレクトロポップ・テイストがオントレンドかつ、広い世代に人気がある理由なのだろうと腑に落ちた。そして、歌メロとラップのシームレスな表現力、トラックのアトモスフェリックなムードに、日本に存在していそうでいなかったAile The Shotaというアーティストのスタートラインを確認できた。
その後、この日のラインナップの中ではポップ/ロック要素を強めに感じられたVaundy、今やジャズシーンのみならず、日本のミュージックシーンにこの人ありな石若 駿のプロジェクト、Anser to Rememberにも大勢のオーディエンスが集結。先程までVaundyでも弾いていたベースのマーティ・ホロベックが駆けつける場面も。管楽器とゲストボーカルをフィーチャーしたスタイルで、millenium paredeでもおなじみのermhoi、KID FRESINO、WONKのステージにも登場したJua、そして極めつけは黒田卓也(Tp)のド迫力のアドリブ。老若男女が熱いソロに惜しみない拍手を送る。そう。そんなシーンが散見されたのがこのフェス最大の魅力でもあった。
THEATRE STAGEに戻り、今やメンバーの名前もフィーチャーするようになったNulbarichのステージに、JQの飾らない人柄、ヒット曲の多いバンドの強みを実感。オーディエンスを大いに躍らせていた。

SOIL&“PIMP”SESSIONS
SOIL&“PIMP”SESSIONSを見るために再びGREEN STAGEへと移動。何やら1曲目からコラージュ的な楽曲が多い印象で、社長のMCによると全曲6月リリースのニューアルバムから初披露しているという。ちなみにステージ袖からロバート・グラスパーが見ていたようで、キーボードの丈青は殊の外緊張したのでは?と社長。後半はゲストボーカルを迎えての展開。まずはAwich、そしてWONKから長塚健斗がORIGINAL LOVEの「ミリオン・シークレット・オヴ・ジャズ」のカバーで参加。アシッドジャズ・テイストの楽曲で長塚の新たな側面も実感できた。社長がステージから捌けようとする長塚を呼び止め、WONKを物販でコーヒーとまな板を売るバンド、長塚を料理人の副業に歌っている人物といじり、会場の笑いを誘う。最後にはしっかりまな板を発注するのも社長の人柄か。さらにSKY-HIとのコラボ新曲を宇宙初公開。エキスペリメンタルな楽曲にかなり驚かされる。こんなふうに予想外のことが頻発するフェスである。

ロバート・グラスパー
世界の音楽史を塗り替えるアーティストから、いわばJ-POPに革命を起こす存在までが並び立つするユニークネス。SKY-HIのファンもヘッドライナーたるロバート・グラスパーのステージに移動していく。まさにこの日の出演バンドのミュージシャンたちが多感であった10代、20代前半に影響を受けたであろう、名盤『ブラック・レディオ 』、その生みの親がグラスパーその人である。タイミングよくシリーズ第3弾『ブラック・レディオ 3』がドロップされた直後の来日、そして同フェスでのヘッドラインはさすがオリジネーターの面目躍如というアンサンブルだった。グルーヴの質がもはや次の世界。特にドラムのジャスティン・タイソンとベースのデヴィッド・ギンヤードのフレージングがもたらすそれはライブを目撃できて良かったと心から思える未知との遭遇だった。ライブの模様は後日オンエアされるそうなので、映像をもってさらに理解を深めたい。
グルーヴ、リズム、音色、ハーモニー。その組み合わせに終わりはない。グラスパー・バンドが残した痕跡は出演バンドのみならず、オーディエンスにも波及し、この場から新しい芽が生まれる予感すらあった。帰路の途中、フレージングについて熱心に話し合う学生らしき青年たちの会話に、このフェスの可能性の一端を見る思いがした。来年はどんなニューカマーが登場するだろう?いまから楽しみでならない。
(おわり)
取材・文/石角友香
写真/中河原理英、岸田哲平、伊藤 郁