松室政哉『Singin' in the Yellow』インタビュー
──2025年は音楽活動の指針に“多幸感”、“ハッピー”を掲げている松室さん。まずは、その想いに至った理由を教えてください。
「以前からやっていた“cafe de MURO”という1人で全国を巡るAcoustic Liveを、去年末から本数を増やしたんです。そこからライブへの向き合い方が変わってきました。と言うのも、前々作のアルバム『愛だけは間違いないからね』(2022年11月リリース)のタイトル曲ができたことによって、ライブ全体の多幸感やハッピーさが、お客さんを巻き込む形でできあがってきた気がして。なんだか、“今、自分がやっていてしっくりくる空気感ってこれだな”というのが、何年もかけてわかってきたんです。そんな中、今年の初めにスタッフと打ち合わせをしたときに、せっかくそういうモードになっているのなら、それを全面に押し出したテーマでやってみるのはどうだろう?となって。確かに“多幸感”、“ハッピー”をテーマにしたことはこれまでやっていなかったですし、人間・松室政哉としても、ここ数年は“ハッピーであることを大事にしたい”という気持ちが強くなっているので、“やってみよう!”と思ったのがきっかけでした」
──今のムードの原点とも言える「愛だけは間違いないからね」が誕生したときのことを覚えていますか?
「もちろんです。今一緒に作っている(作詞家の)金木和也と初めて2人で作った曲です。ちょうどコロナ禍で、ライブとかも一旦全部なくなった時期で…。彼はもともとシンガーソングライターなんですけど、“作詞家になりたい”と聞いてたので、“じゃあ、リリースとか関係なく一緒に作ってみようよ”と言って作ったのが、「愛だけは間違いないからね」でした。自分一人では出てこない空気感でもあったし、金木は金木で“松室が歌うなら”を考えてくれていて、“こういうふうな曲を僕が歌っていいんだ”と教えてくれた気もしました。それこそ、曲ができた後にウクライナの戦争が始まったり、コロナがもっと深刻になっていったりしたので、「愛だけは間違いないからね」のテーマ性が、自分の中でより明確になってきたっていうのはありました」
──“多幸感”や“ハッピー”をテーマにここまで活動してきての手応えはいかがですか?
「“お客さんもしっくりと受け取ってくれているな“って感じがしています。それによって、この方向性が間違ってなかったという感覚もあります。ライブでも、若い頃はもっとカッコつけたかったり、もっとモテたいとかもあったりしたと思うんですけど、今はそういうのより、ちょっとダサい部分を見せてでも笑ってもらえるというか、幸せな空間を作れるほうが、僕がやるエンターテインメントとしては理にかなっている気がしているんですよ」
──9月にリリースしたアルバム『Singin’ in the Yellow』はそういうムードの中で誕生した1枚かと思いますが、制作にあたってまずはどこから着手した感じですか?
「アルバム全体のというよりかは、2025年のテーマを決めて、最初にリリースしたのは「人生はロマネスクさ」でした。MVも今までになかったテイストというのもあって、それがいきなり“ハッピーブースト“みたいな(笑)。次にリリースした「コンバート」はアニメのタイアップだったこともあって、制作としてはかなり前に済んでいて。なので次が「渚のメイキャップ」ですね。これも打ち合わせで出てきた話で、スタッフから“松室の音楽的に、80年代90年代のシティポップが合うんじゃないか?”って。それでやってみると、自分の中でもかなりハマったんです。最初はオメガトライブみたいな感じをイメージしたものの…着地したらサザンオールスターズになっちゃいました(笑)。でも、そこが自分のルーツなので。ただ、そういうのも、どストレートにできたってのが新たな発見でした」
──以前の松室さんだったら、打ち合わせで出たスタッフの方からの提案に素直に頷けなかったかもしれない?
「かもしれないです。「渚のメイキャップ」はある種のオマージュで、そうなるとさっき言った“カッコつけたい”ってところから離れていくじゃないですか。でも、むしろ(聴く人に)喜んでもらいたいから、そういうテーマの曲が夏にできあがったのは大きくて。打ち合わせでその話が出てこなかったら作っていなかったと思います。でも、これもライブでお客さんが作ってくれる空気感であったり、自分の中の変化であったりによって素直に着手できたというか…で、実際に着手してみたら、あまりにも自然な流れでした」
──ここからは、アルバム『Singin’ in the Yellow』の収録曲についてお伺いしていきたいのですが、まずは1曲目の「未来ある馬鹿者からのセイハロー」。歌い出しの<ハロー世界>を聴いた瞬間、世界を明るく照らしてくれるようなパワーワードだと感じました。
「本当にそうですよね。“多幸感、ハッピー”をテーマにすることって、今のこの世知辛い世の中への、ある種アンチテーゼなわけじゃないですか。“鬱屈したムードがあるから、こういうテーマにしよう“となるわけで。でも、そこで<ハロー世界>って、根拠も何もないけどそう言ってくれるヤツが横にいるだけで、たぶん少しはラクになれると思うんです。僕がずっと言っているテーマ性を金木が汲んでくれたのが、まさにこの歌い出しの1行に表現されていると思って。この歌詞を見てブルブルと震えましたし、これまでずっと一緒に作ってきて、作詞家と作曲家としてだけではない特別な関係性が築けている嬉しさを感じた瞬間でもありました」
──そんな金木さんが歌でも参加している3曲目の「ふたりよがり feat. 金木和也」は、最初から一緒に歌う想定だったんですか?
「いえ、最初は特に何も決めていなくて…もともとのテーマとして、ドライブミュージック的なサウンドでアーバンな曲をイメージして作り始めました。いわゆるラブソングなんですが、見方によっては、僕と金木が2人で(曲を)作っているときの空気感に似てるというか…“誰にも何も言わさないぞ”みたいな(笑)。彼はそんな意図は多分ないと思いますけど(笑)、レコーディングで歌いながらもそういう感じを抱いていました。それで、どうして金木が歌うことになったかと言うと、デモの段階で、少し譜割がわかりにくいところに金木がガイドとして仮歌を入れてくれたんです。それが耳に馴染み過ぎて、“このまま金木に歌ってもらったほうがいいよな”と思って。お願いしてみて断られたら1人で歌おうと思っていたんですけど、快く歌ってくれました」
──そうだったんですね。そして、「世界中を敵に回しちゃうな」は、“松室さんがこういったタイプの楽曲を歌うんだ!”と、新鮮でした。
「そうですよね。この曲に関しては僕1人では絶対に出てこないテーマというか…完全に“金木ワールド”です。ただ、これこそ蓋を開けてみれば“サザンっぽい“と思ったりして。曲が完成して、“僕は当たり前にサザンを聴いていたのに、どうして自分で作ってこなかったんだろう?”みたいな(笑)。もしかすると、この曲を聴いて驚いた人もいるかもしれないですけど、ライブでやってもスッと自然にできますし、テーマとしてもこのアルバムに合っています。フレーズもキャッチーなものの連続…と言っても、都市名とかなのでキャッチーも何もないんですけど(笑)」
──でも、都市名にしろ、2番で登場する生き物にしろ、何をピックアップするかによってキャッチーさも変わってくる気がします。
「そうなんですよ。で、生き物のところで3行目に<渦巻く宇宙の力や何かのサナギまで>という部分があるんですけど、金木が最終で出してきた歌詞ではここもまだ生き物の固有名詞が続いていたんです。“それもオモシロいけど…”と思ったんですけど、ファイルの端っこに金木が消し忘れていたメモ書きがあって。それがこの1行でした。本人としては、本当はメモ書きに書いてあった<何かのサナギ>のほうがいいんだけど、そうするとこれだけ生き物を連呼したのに、最後に諦めたように聴こえるかも?と思ったらしくて…。でも、僕的には<宇宙の力>と言っておきながら、名前もわからない<何かのサナギ>っていう、その視点の動きが映像のようでしたし、“これ以外ない!”と思って変えてもらいました。彼がメモ書きを消し忘れていなければ、この歌詞はなかったです」
──「世界中を敵に回しちゃうな」のサウンド感でイメージしていたものは?
「最初はピチカートファイブとか、そういうオシャレな感じをイメージしていたんですけど、出来上がったらまたサザンになっていました(笑)。「太陽は罪な奴」とか、そういうテンションに…(笑)。でも、そうなるのは僕がサザンを聴いていたからで、ある意味、松室っぽくなったと言えるので。楽曲を作るときは毎回いろいろ考えるんですけど、どこから入っても、ちゃんと自分らしさが出る。そんな自信を持ってやっている感じはあります」

──松室さん自身が制作で特に印象に残っている楽曲はありますか?
「「うるう」です。この曲は、他の曲と比べると、隠と陽なら隠のテイストになりますが、サウンド的にはライブで、生バンドでやると盛り上がるだろうなっていうワクワク感をずっと感じていました。だったら(アルバムに)入れようってことになって。これは金木もかなり迷ったみたいです。隠のテイストだけど、多幸感やハッピーをテーマにしたアルバムに収録するにあたって、どこまでそっちの方向性に行くのか…そこについてはいろいろと話しました」
──確かに、あまりに隠だと今作のハッピーさが削がれてしまう気もしますし、さじ加減が難しいですよね。
「そうなんです。でも、歌詞のテーマは、踊れるリズム感に乗っかって開き直るようなところもあるので、そういう捉え方をすると意外と今回のアルバムにもハマると思いましたし、他の曲のハッピー度も目立ってくると思って。そういったスパイスになる曲になるといいなとは思っていました」
──そして、大切なタイトル曲「Singin’ in the Yellow」。イエローというのは、やはり幸せをイメージした色になりますか?
「はい。映画『幸福の黄色いハンカチ』じゃないですけど、日本においては黄色って幸せな色というイメージがあるので。このイメージカラーはアルバム云々の前に、今年の活動テーマを“多幸感”、“ハッピー”にした段階で決めていました。なので、自然とアルバムを作るときにも“Yellow”が。で、『雨に唄えば(Singin’ in the Rain)』からのオマージュも込めて『Singin’ in the Yellow』に…パッと思いついたものではあるんですけど、“いいんじゃないか”というので決まりました」
──“多幸感”や“ハッピー”をテーマにすることは、ある種、今の世の中へのアンチテーゼとおっしゃっていましたが、そういう中で完成したアルバム『『Singin’ in the Yellow』』は松室さんにとってどんな1枚ですか?
「それで言うと、こういうアルバムができあがったのは今の世の中の空気感があるからなので、それって喜ばしいことではないんです。本当は世の中が楽しいほうがいいに決まってますから。でも、結果論として、そういう世の中の空気感があるからこそ、このテーマ、このアルバムですし、松室として今、この2025年に入れたい音楽が入れられたので、そこはすごくよかったと思っています」
──時代の空気感を汲み取って作られた作品は、リスナーとして共にこの時代を生きている感覚を強く得られると思います。
「そうですね。そこを明確にしておけば、このアルバムを5年後、10年後に聴いたときに、2025年の空気感を思い出せるような気がします。新しいサウンドをやっているというより、今の世の中の空気感をアルバムに詰め込むことが、こんなに意味のあることなんだというのは、今まではそこまで考えることはなかったですけど、今回、このアルバムを作って思ったことの一つでした」
──アルバムに対するファンの方の反応はどんなふうに届いていますか?
「先日の“Augusta Camp 2025”で「世界中を敵に回しちゃうな」とかを演らしてもらって(※)。“どうした、松室!?”と思った人もいるかもしれないですけど、そこでしっかりやり切ると、案外受け入れてくれるんだという感覚がありました。特に“Augusta Camp”は音楽好きのお客さんが集まるので、その人たちがどんなふうに受け取るのかな?って僕もドキドキでしたけど、自分がやりたいテーマとかメッセージを明確に持っていれば、音楽好きな人にこそ伝わるんだなって。あと、こういう曲が1曲あるだけでライブも一気にカラフルになるので、アルバムを聴いてくれたファンの人たちは今度のワンマンライブを楽しみにしてくれていると思います」
──事務所の先輩・後輩ミュージシャンの方々の反応は?
「これまで“Augusta Camp”での松室は、バラードとか比較的優等生っぽい曲を歌うことが多かったんです。でも、今年は「世界中を敵に回しちゃうな」とか「渚のメイキャップ」のようなテイストの曲を詰め込んでみました。なので、先輩たちの反応もどんなかな?と思っていましたけど、みんな面白がってくれました。スキマスイッチのシンタさん(常田真太郎)は前日のリハを見て、“これなら明日はこういうふうにしたほうがいいよ”ってアイデアを出してくれたりもして。だから…やっぱりやり切るって大事ですね」
──“やり切る”というのは、恥ずかしがらないという意味合いに近いのでしょうか?
「そうですね。「世界中を敵に回しちゃうな」を初めて披露したのが“Augusta Camp”だったんです。なので、どうしても“大丈夫かな…受け入れてくれるかな…”と思ってしまうんですけど、あれだけ受け入れてもらえたので、次以降は何も怖くないです(笑)」
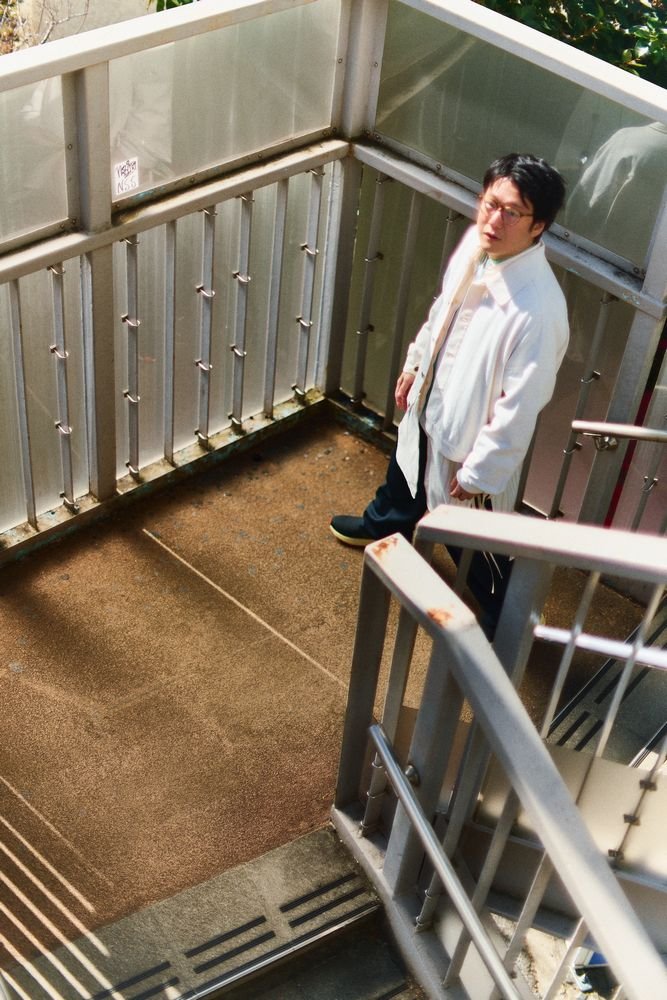
──2025年も残すところあと2か月弱ですが、どんな1年でしたか?
「今年2月にやった“LABORATORY”のライブが遠い昔に感じます。その後の“cafe de MURO”ツアーも27公演。それを怒涛に駆け回って、その間にアルバムを作って、さらには思いもしなかったジャカルタでライブもやって…。もちろん嬉しいことなんですけど、もう、わけがわからないです(笑)。本当に濃厚な1年間でした」
──ジャカルタでのライブはいかがでしたか?
「なんか…不思議な空間でした(笑)。でも、一つ明確に感じたのは、インドネシアの人は本当に音楽好き。僕のことなんて知らないと思うんですけど、ステージに出て行って歌い出したら、みんな集まってきてくれて。コール&レスポンスも、なんなら日本より盛り上がったくらいでした(笑)。“そこにある音楽”をちゃんと聴いてくれるのは素晴らしいと思いました。行く前は心配だったんですけど、行ってみたら楽しかったです。しかも、日本から来てくれた方もいたんです…頼もしかったです。“こんなところまで来て大丈夫なの!?”って心配になりましたけど(笑)、やっぱりいつも来てくださる方たちがいるっていうのは心強かったですし、そのおかげで落ち着いてライブできたので、本当にありがたかったです」
──そして、今月29日にはバンド編成のワンマンライブ『Matsumuro Seiya Live 2025 "Singin’ in the Yellow"』が東京・渋谷で開催されます。どんなライブになる予定ですか?
「アルバムを掲げてのライブなので、もちろん『Singin’ in the Yellow』の曲は総ざらいします。とはいえ、今年から松室のことを知ってくれた方とか、ライブに来るようになった方とかが増えてきている感じがしていて、今回が初の松室のバンドワンマンっていう方、あるいは久々に来ていただける方も多いと思うんです。なので、そういう人たちにもちゃんと喜んでもらえるような、なおかつ、いつも来てくれてる人たちにも喜んでもらえるように。アルバムを提げたライブではあるんですけど、そこのハイブリット感も考えたセットリストにしたいと思ってます」
──そのあと、オフィシャルファンクラブ「むろ村の集会所」会員限定にはなりますが、12月21日に江ノ島で開催される“むろ村の忘年会 2025 in 江ノ島〜江ノ島サンセットライブ 冬編〜”についてもお聞かせください。昨年の忘年会の様子を拝見すると、すごく楽しそうでした!
「昨年はライブの後、いわゆる忘年会のようなことをやったんです。そのときはギターのゾノさん(外園一馬)がいたので、ゾノさんが弾くギターでお客さんが歌う贅沢なカラオケ大会みたいなこともしました。そんな場で手を挙げる人なんていないだろう…と思ったら、たくさんいました(笑)」
──アットホームな雰囲気がたまらないですね(笑)。ファンクラブのみなさんの存在って、松室さんにとってどういうものですか?
「ファンクラブ「むろ村の集会所」は昨年に発足したんですけど、その存在が今のこの空気感を作るのにとても大きいと感じています。みんなが作ってくれたこの空気感を、こういうふうにアルバムであったり、ライブであったりに出せるので。みなさんへの感謝の意味も込めて今年の忘年会もいろいろと企画を考えているんですけど…12月21日ですよね。ちょっと心配事なのが、M-1グランプリの決勝がその日になるかどうか。まだ発表されてないですけど、例年、いつもこの辺りなんですよ。もし日程が重なった場合は、絶対に松室に結果がバレないように、みなさん口を堅く結んでおいてください(笑)」
(おわり)
取材・文/片貝久美子
常田真太郎(スキマスイッチ):アルバム『Singin’ in the Yellow』コラム

「先輩、これ新しい音源です。聴いてください!」
「いや、CDは間に合ってる間に合ってる笑」
「いやいや、それいつものやつじゃないですか!笑」
そんなやりとりを毎回しては、今まで数枚の松室の新しい音源を聴いてきた。人から頂いた音源はその方のキャリアに関わらず必ず全部聴く――というKANさんの姿勢を聞いて、出来るだけ“KANイズム”を継承していこうと常々思っている僕は、もちろん松室の今までの音源もいつも楽しく聴かせてもらいながら、お節介だとは思いながらも自分なりに分析なんかをしては本人に伝えてたりしていた。
ただ、ずっと気になっていて、それこそ毎回彼に直接言ってきた言葉がある。
「今回は自分で出来たの?」
そう聞くと松室は決まって「いえ、この表題曲は○○さんにアレンジしていただきました!」と、いつも少しはにかみながら答える。僕はその返しの言葉の裏側にあるであろう気持ちを察してはいるのだが、やはり少しの意地悪と期待を持って、なんだか毎回そう言ってしまうのだ。
スキマスイッチと松室の関係を確たるものにしたのは、おそらくスキマスイッチのツアー「TOUR 2018 “ALGOrhythm”」で彼がオープニングアクトを務め、全国を一緒にまわったことだと思っている。あの時「きっと愛は不公平」を表題曲としたEPをプロモーションするために、毎会場アコギ一本で歌いあげてきたわけだが、とある公演の打ち上げで話してくれたことがとても印象的で、強く記憶に残っていることがあった。
松室は、もともとインディーズ時代は基本的にセルフアレンジ・セルフプロデュースで、作詞作曲もこなしながらサポートミュージシャンなどを自分で選びつつ、自分一人で判断し完結していくスタイルで活動していた。だが、メジャーデビューが決まったあたりから少し風向きが変わった。
デビュー曲に関しては、いわゆるプロのアレンジャーにお願いをしてプロレベルに楽曲を仕上げてもらい、華々しくデビューを飾って活動のスタートに弾みを付けるということがよくある。これは全く珍しいことではなく、特にバンド形態で活動している人たちにとっては割と普通にあることだ。メジャーデビューという、それまでの枠組みがいきなり大きくなり、聴いてもらえる人の数も段違いで増えることから、そのタイミングで楽曲や音のクオリティを数段上げ、その基準値をもって活動していく。こうしてバンドやアーティストの全体のレベルも上げていくという、いわば業界標準のデビュー戦略でもある。
松室のデビューにそういう戦略があったかどうかは詳しくは聞いていない。だが、おそらくデビュー時にプロのアレンジャーさんを起用するというのは、少なからずそうした意図もあったのかもしれないと個人的には感じた。(しかも、そのアレンジャーさんが超有名プロデューサーだったのも余計にそう思った要因だった。)
補足しておくと、このセルフアレンジ・セルフプロデュースについては、それをするしないにあたってどちらが優れているということではない。出来る出来ないで言えば、出来た方が予算もかからないので事務所やレコードレーベルは喜ぶとは思う。スキルとしては特殊技能に近いものなので、身に付けた方がよりミュージシャンとして音楽を楽しめるようになる。が、セルフプロデュースでなくても大ヒットを飛ばす人は星の数ほどいる。
大事なのはそのアーティストの名前であり、素晴らしい楽曲を世に放って、より多くの人に聴いてもらえることだ。やり方は人それぞれである。
松室の話に戻すと、デビュー曲はプロのアレンジャーを迎えたが、カップリング曲は変わらずセルフアレンジ・セルフプロデュースで制作したものだった。僕が印象に残ったのは、このあたりの松室の捉え方だった。
彼は、要するに自分の実力が足りていなくて表題曲のアレンジができなかったと思っていたらしい。それについてはマネージャーや事務所の意向もあるので僕がとやかく言うところではない。だが、松室がそう思っているなら――「デビュー曲からセルフアレンジ・セルフプロデュースでやるつもりだった」と考えていたなら、それが実現されなかった時の感情はものすごく悔しいものになると同時に、ミュージシャンとしてこれから伸びていく大事な芽が出た瞬間でもある。
僕はその話を聞いた時から、松室の背中を押す、いやお尻をつつく程度の立場になろうと決めて、毎回例の質問をしていくことにしたのだった。
一枚目のアルバム『シティ・ライツ』は、錚々たるアレンジャー陣によるシングル曲と、松室自身がアレンジした曲とが融合した作品になった。
二枚目のアルバム『愛だけは間違いないからね』は、同じアレンジャーさんとの共同作業による集中力の高い作品になった。
三枚目のアルバム『LABORATORY』は、そのタイトル通りにコラボを中心とした実験的な楽曲が多く、それこそ福耳として僕も参加させてもらった。
ミュージシャンクレジットを見るのが習慣になっている人はお気づきだと思うが、三枚ともかなりの数のサポートミュージシャンが参加しており、松室の楽曲を彩ってくれている。しかもその中で松室自身のアレンジ曲が良いアクセントとなり、アルバム全体でうまくバランスをとっているのも聴きどころだと感じていた。
しかし、まだ「全部自分で」というアルバムは僕の元には届いてきていなかった。
そして9月のオーガスタキャンプのリハーサル終わりで(冒頭のやりとりの後に)、松室本人から手渡された『Singin' in the Yellow』。実はこの時、僕からのあの質問はなかった。手渡される時に「今回は全部自分でやりました!」と満面の笑みで松室が僕に言ったからだ。
「そうかそうか!よかったな!」と返しとしては軽い言葉で返したのだが、内心は違った。僕は心の中で、作った本人でも無ければスタッフでもないのに勝手にガッツポーズをして飛びあがっていた。聴く前にハイタッチをしてしまうような気持ちだった。
ただ、音はどうか。曲はどうか。クオリティはどうか。こればかりは聴かなければわからない。それこそ少し厳しい見方をすれば、予算の都合でセルフにしたなんてこともありえなくもない。
別に音源を聴く時にわざわざ感じなくてもいい不安と、でもついにこの時が来たのかというなんだかわけのわからない到達感を完全に松室に対して勝手に抱いていた感覚は、1曲目から完全に、いとも簡単に、音の波によってサーッと不安だけが消えていった。
少し話が逸れるが、「やりたいこと」を“楽しく”表現するのは難しい。僕は常々「やりたいこと」「やれていたいこと」「やれてること」は違う、と言ってきた。
例えば自分で言うなら、「やりたいこと」はクラシックのようなオーケストラアレンジだったり、流麗なピアノの旋律を奏でることだったり、ジャズ的なアプローチだったりする。これはまだ出来てはいないこと―いわば目標だ。
「やれていたいこと」はポップスのアレンジだったり、ライブで相方の歌を支えるピアノだったりする。これはまだ不確かで他人からの評価も関係してくるので、自信と信念と願望が入り混じる。
「やれてること」は作詞作曲や音源制作、譜面作成だったりする。これはいわば実力や実績だ。
「やれてること」を土台に「やれていたいこと」を継続・追及し「やりたいこと」に挑戦していく。
この三つを常に分析して足りないものを勉強し、成長していきたいと思っている。ただ、大事なのはそこに「楽しさ」があるかどうか。これが本当に難しい。楽しいと身に付く時間も段違いに早いし、リスナーに届く時のテンションもいい方向に運ぶことが多い。だが、コントロールするのもかなり大変だ。
難しいことやレベルの違うことをやろうとすると、全く太刀打ちできずにストレスが溜まる。かといって今「やれること」だけで活動しても進歩や成長はない。きっとこれはミュージシャンに限らず、部活や仕事や育児など、心身共に成長することがテーマの全てのことに当てはまるのではと思う。
何が言いたいかと言うと、今回の松室のアルバム『Singin' in the Yellow』は、その「やりたいことを”楽しく”やって」出来たアルバムのような気がしてならない。
もちろん高負荷なストレスもあるだろう。失敗やミスもあるだろう。期せずして出来てしまった実力外のこともあるかもしれない。
でも、このアルバムに収録されている曲たちを聴いていると、松室が「あーでもない、こーでもない」と、まるで子供がたくさんのレゴブロックの中から今まさに頭の中で描いているものを作り出そうとしているような、純粋無垢な想像力に満ちた顔が浮かんでくる。
セルフはとにかく時間がかかる。演奏も自分ならその楽器のプロではない分、より手間がかかる。その判断も自分なわけで、もちろんそうなればその分の時間が足されていく。マネージャーやディレクターを待たせることにもなる。
でも、やっぱりその道のりで成長していけるし、自分でやってしまった失敗やミスなら栄養にしていける。そして何より、完成した時の気持ちといったらそりゃもう格別だ。さらにそれがたくさんの人の耳に入ってくれれば、なおさらだ。
「自分でやるのは責任もあるし大変ですけど、でも楽しかったです!」
この言葉を松室から聞けて本当によかった。そしてそのアルバムが素晴らしくて、さらに良かった。
…本当は一曲一曲について語りたいところだが、なんとなく立場上それはあまり良くないと思うので、この文章を書こうと思い立ったのはアルバム三周目で「渚のメイキャップ」を聴いた瞬間だった、と書いておくことにする。
少し寂しいけど、もうお尻はつつかなくていいに違いない。
今はここからの松室の世界が深く、濃くなっていくのが楽しみで仕方がない。
常田真太郎
RELEASE INFORMATION

松室政哉『Singin’ in the Yellow』
2025年9月3日(水)発売
通常盤(CD+DVD)/UMCA-10162/5,830円(税込)
LIVE INFORMATION

Matsumuro Seiya Live 2025 "Singin’ in the Yellow"
[出演]
松室政哉
[バンドメンバー]
Dr:伊藤哲平
Bs:佐藤慎之介(ZION)
Gt:加部輝(ウルトラ寿司ふぁいやー)
Key:石田玄紀
Mp:橋本裕充
日程:11月29日(土)
会場:東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
OPEN / START:16:00 / 17:00
U-NEXT
11月29日にSHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて開催される『Matsumuro Seiya Live 2025 "Singin’ in the Yellow"』の模様をU-NEXTにてリアルタイムで独占ライブ配信いたします。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。
圧倒的なメロディーセンスと映画のワンシーンのような詞世界、それらを包み込む優しく儚い歌声が聴く者の心を掴む松室政哉。
映画フリークでも知られる松室政哉が元・映画館の会場を舞台に繰り広げる、2025年を総括するバンド編成ワンマンライブを、U-NEXTならではの高画質&高音質なライブ配信でお楽しみください。

Matsumuro Seiya Live 2025 "Singin’ in the Yellow"
配信詳細 >>>
配信時間
ライブ配信:11月29日(土)17:00 ~ライブ終了まで
見逃し配信:配信準備完了次第~12月5日(金)23:59まで
配信公演:11月29日 SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください
独占を含む松室政哉 ライブ映像を配信中!
・「Augusta Camp in U-NEXT ~Favorite Songs~」Vol.11
・Matsumuro Seiya Live 2023 "愛だけは間違いないからね" ~Joyful! Joyful!~
・Office Augusta 30th MUSIC BATON Vol.6 松室政哉『F.O.M』
・Matsumuro Seiya TOUR 2019 “City Lights”
特集ページ








