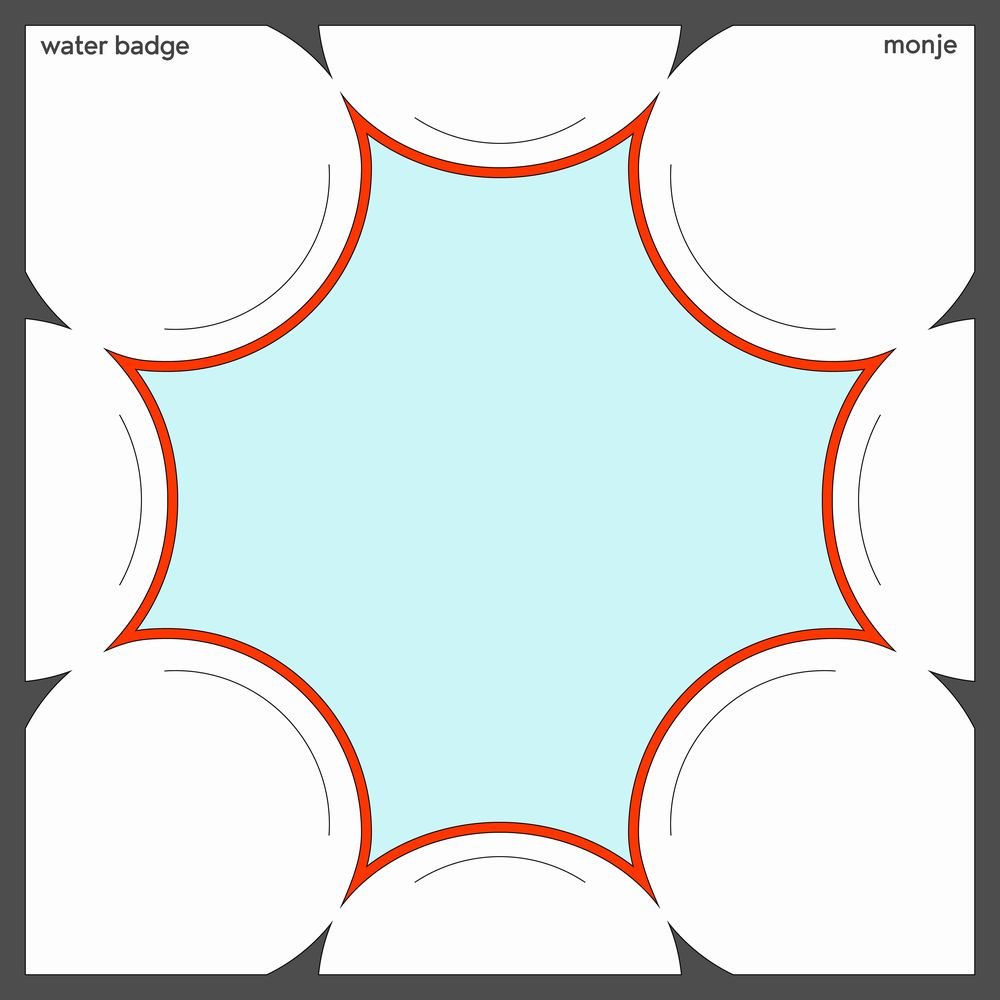──1st DIGITAL ALBUM『water badge』がリリースされていますが、制作前はどんな作品にしたいと考えていましたか?
「初めてのアルバムなので、自分たちのターニングポイントになったような曲を集めてリリースしてもいいかな?と思っていました。『衣食住』と『遊歩道』という2枚のEPから選曲した曲と新曲をまとめる形で、monjeの“これまで”と“これから”も感じさせるようなアルバムにしようと考えていました」
──全12曲の中で“これまで”を特に象徴する曲を挙げるとすると?
「アルバムの後半に1st EP『衣食住』の曲が固まっているんですけど、その6曲は自分たちの中でもすごく思い入れが強いです。その中でも2022年8月にリリースしたデビュー曲「Sangria」には、“何にも知らないけどとりあえず音楽を作るぜ!”みたいな(笑)。原初的な感じが現れているとも思います。自分たちが音楽を作るきっかけになった「Heya」も収録していますし、アルバムの後半に自分たちのコアな部分を持ってきているイメージです」
──「Heya」はもともと東京藝大在学中、大学2年生の夏に課題として作った曲でした。
「そうですね。当時はコロナ禍で鬱々とした環境の中で大学生をドンピシャで過ごしていた代だったので、今、振り返ってみると、時は進んだなと思います。そういう意味では、自分たちのいろんな記憶が詰まっていますし、いいスタート地点になったと思う部分があって。コロナ禍という環境もあったんですけど、「Heya」というタイトル通りに、自分たちの手の届く範囲から豊かにしていこう、みたいな意識がありました。そこから、アルバムの1曲目に入ってる「あつまれ」に向かう過程で、意識がどんどん外に広がっています。部屋という自分たちの暮らしの中からスタートして、どんどん広がりを持つっていう意味では、ヒストリーとしていいスタートだったと思いますし、いつ振り返っても、“いい一歩目だったな”って思える曲だと思います」
──出来た順番は逆になりますが、デビュー曲として、「Sangira」が先にリリースされました。
「世界で争いが始まったタイミングで作っていたんですけど、それは、大学の中でも相当ショッキングな出来事だったんです。アートや美術の業界にいる中で、あらゆるアーティストさんたちが表現していく上で揺らいでいた時期だったっていう記憶があって。自分たちはどういうものを作ったらいいか?って悩んで作った記憶があるんです。自分が持つアイデンティティとしてのグローバルな経歴もあって…」
──Kananさんはスペインとブラジルに留学した後に日本に帰国して、藝大に入学しているので、よりボーダレスな感覚を持っていますし。
「そうですね。国境というのはあるんですけど、人と人が関わる中では世界の境界線はないものと個人的には感じていて。そういうところを自分なりに表現できたらいいなと思って、多言語の曲にしました。何を言っているか分からないけど、心地よく口ずさめるようなフレーズがあって、英語になったり、日本語になったり。争いが始まったという状況下で自分のアイデンティティを色濃く反映させた曲だったっていう意味ですごく記憶に残っています」

──そして、“これから”を象徴するのが新曲の3曲ですよね。
「1st EP『衣食住』の後から外に出るような曲をかなり意識していました。今回、もう1つのコンセプトがあるんですけど…」
──それなんですか?
「改めて振り返ると、monjeはジャンルをとても意識して曲作りをしていたなって思うんです。曲作りの最初に必ずジャンルを決めていたんです。どうしてかというと、クリエイティブしていく中で途中で“いきすぎてない?”って考える時があって。そういう時に一旦立ち止まって、最初に決めたジャンルに戻ってみることで、自分たちが今どのくらいまでいっているようなのかがわかるんです。そうしてジャンルっていうものを意識することによって、むしろ遠ざかることもできるし、近づくこともできるし、意識した上ではみ出す面白さみたいなものも作れるんじゃないか?って思ったんです。monjeのこれまでの曲を通して常にその意識をしていました」
──なるほど。
「だから、今回は“badge”っていう肩書きと、流動的な“water”という対極にあるようなものを1つにして、造語的な形で『water badge』というタイトルにしています。今回の新曲3曲に関しては、ジャンルという枠組みを意識しながらも、そこからどれぐらいはみ出せるか?を意識して作りました。例えば、「Marrakech」がバラードで、「Coyote」はドライブに合うような曲にしようというふうに最初に決めて」

──では新曲3曲をPV公開順にお伺いしたいと思うんですが、まず「Kempa!」は?
「「あつまれ」の次にリリースする曲で、時期も春にあてたいという気持ちがありました。最初に“遊び心”があるような曲をもう1曲作ろうと決めていました。「Kempa!」は、“遊び”をテーマにした2nd EP『遊歩道』や「あつまれ」を経て、誰かと話をしながら作っていくことで、誰かを介入させた中で生まれることを大事にしているっていう気づきから生まれた曲です。知り合いの洋服デザイナーさんと会話をしていく中でお互い共感したことや大事にしていることを共有しながら、それをキーワードに曲を作っていったんです」
──共感したキーワードというのはなんだったんですか?
「「あつまれ」や「MUTEKI」とも共通する部分があるんですけど、簡単にいうと、歳を重ねて、大人になっていくことへの漠然とした焦りです。デビューしたての時は大学生だったわけですけど、卒業してしばらく経っていて…。例えば、同世代の人と初めて出会った時に、大学生の時は大学生同士という共通項があって無条件にフラットに接することができました。でも、学生という身分から社会に一歩出ると、いろんなところで肩書きや地位というものに出くわしますし、同い年でもあってもその違いが、見たくなくても見えてしまいます。そこに対して、前のめりで突っ掛かっちゃうような焦りが出てきて。その方とは全然違う業種ですけど、“同じようなことを悩んでいるんだ“っていう共感がありました」
──なるほど。肩書きや地位は“badge”とも通じますね。
「そうですね。同じ悩みを共有する中で、“じゃあ、洋服をデザインするときにどういうことを大事にしているんですか?”って聞いてみました。彼は去年5月に開催したワンマンライブ『monje第一公園』の時に森山くんが着ていたベストを作っている方なんです」
──あの、うにょうにょの?
「そうです(笑)。ワンマンライブを見に来てくださっていて、そこで出会って、意気投合しました。彼は“人はそれぞれ形が違うのに、洋服のパターンやサイズが決まっているのは不思議だと思っている”と話していて。その型をどう逆手にとって、全然違う形にできるか?…“いろんなパターンを研究しながら面白い形を作っている“って話をしてくれて。自分も大学で『身体の在り所』を研究していたのもあって、とても興味深かったんです。しかも、”自分のクリエイティブによって焦りを解消している“というとこも共感できたので、その時に”大事だな“と思ったキーワードから作り始めたんです。冒頭の<型破り>や<足枷>から引っ張ってきていますね」
──<枠枠飛び越えて>はワクワクという“遊び心”も感じますし、ジャンルという枠を飛び越えていこうとういうふうにも聞こえます。
「そこもすごく意識していますね。歌詞の言葉は割と思い悩んでいるようではあるんですけど、明るいサウンドに乗せることで面白いバランスになるかな?と思っていました」
──PVはどんなイメージでしたか?
「今回のアルバムは、“内向き”と“外向き”、“これまで”と“これから”、“badge”と“water”、そして、“ジャンルという枠組み”と“monjeとしての新たな形”の架け橋になるようなものを意識しています。だから、ジャケットも含めて、映像やビジュアル面は全て外部のクリエイターさんと一緒にものづくりしていきたいと思っていて」
──“monje”と“クリエイター”が楽曲という架け橋で繋がっている?
「そうですね。自分たちでやりたい性分なので、これまでは自分たちで作ってきちゃったんですけど、今回は架け橋っていうところを意識することによって、外部の人とクリエイティブした時の化学反応に期待して、“いろいろやってみよう”っていうことになりました。PVも外部のアニメイターさんと一緒にやりました」
──新曲のPVは全部、アニメーションになっていますね。
「最初に曲と一緒に、“私たちがどういう想いを込めて作ったのか?“っていう文章をお送りしました。”あとは、自由に作ってください“というお願いの仕方だったんですけど、「Kempa!」はとてもポップに仕上げてくださって。それ自体がすごく発見でした。それぞれのクリエイターさんから、どういう映像が上がってくるんだろう?というドキドキは今までのmonjeにはなかったやり方だったと思います」

──続いて公開された「Coyote」は“ドライブ”がテーマでしたね。
「そうです。今まで一緒に音楽をやってきたみんなで家に集まって話をしながら作ったんですけど、コンセプトを決めていく中で、“ドライブソングといえば、疾走感だよね”っていう話になって。その時に、いつも都内をスケボーで移動している森山くんが、“それをクルージングっていうんだよ”っていう話をしてくれたんです。車が通れないような道や自転車でも行けない路地裏を身一つですり抜けていく。すごく自由な感じがして、車や自転車とは違った景色と疾走感があるっていう話を聞いたんです。それって面白いし、森山くんがクルージングしている姿は、みんなが共通して思っている彼のイメージだなってなって」
──だからPVも夜の首都高をドライブしている映像にならなかったんですね。
「そうです。スケボーでのクルージングをモチーフにして、都市をすり抜けるイメージで作っています。それをくみ取ってくださって、街中をすり抜けるようなカッコいい映像を描いてくれたんです」
──タイトルは「Coyote」ですが、森山くんはコヨーテっぽくもあるんですか?
「サビの<コヨーテコヨーテ>は森山君が最初のデモで勝手に口ずさんでいたんです。ここだけは、どれだけ考えても、それ以上にいい歌詞が出てこなかったので、森山くんの仮歌を採用しました。その後で、コヨーテがどんな動物だったかを調べてみたら、すごく面白い動物なのがわかって。ナワトル(北米大陸の先住民)語で“歌う犬”という意味があって、足が速いから疾走感があるし、一匹狼みたいな感じも森山くんとちょっと似てるんじゃないかな?って思います」
──そして、今週、PVが公開されたばかりの「Marrakech」はバラードでいいですか?
「最初に“バラードソングを作ってみよう”ってなったときに“もう少し設定があってもいいな?”と思って。“よくわからないワードが急に出てくる曲って、ちょっとSFっぽいよね“みたいな話にもなって。SFチックな設定と恋愛を組み合わせたストーリーラインを考えていきながら、もう情景で書いていったイメージです」
──失恋ですよね。
「失恋と言ってもただの失恋ではなく、“距離”をテーマにしていて。勝手な持論なんですけど、いわゆる遠距離恋愛って、東京と埼玉でも、日本と海外でも、別に一緒だと思っていて」
──あはははは。何が一緒ですか?
「“距離がある”ということがもう一緒だなって。近くても遠くても、距離があるってことは、そこから先の感情は一緒なんじゃないか?って。近未来的で極端な話ですけど、もしも地球と火星ぐらい距離が離れたとしても、結局、距離があるということで覚える寂しさは変わらないと思うんです。遠距離恋愛は、距離に関わらず、全ての遠距離恋愛で必ず同じ感情になるっていう面白さと不思議さ、それに、普遍性を感じていて。未来でも遠距離恋愛はきっと現代と同じくらい寂しい気持ちになるんだろうなっていう設定で書きました」
──宇宙を舞台にした曲に、マラケシュというモロッコの都市をタイトルにつけたのは?
「ちょっと異国的なサウンドを作りたいっていうのと、マラケシュは自分が訪れて一番記憶に残っていて、良かった街だからです。熱気があって、みんながぎゅうぎゅうの中でいろんな音がして、いろんな匂いがして。カオスなんですよ。ほんとうに面白かったですし、すごく良かった街でした」
──映像にあるベッドですぐにマラケシュに旅立てるというイメージですか?
「そうです。“異国感を意識してほしい“っていうオーダーはしていました。作家さんが最初の<ベッドは舟になって>いうワードを気に入って作ってくださいました。<ベッド>っていうところをキーワードにしてくださっているんですけど、最初は2人から始まっていて、次のシーンで1人になって。最後のシーンではベッドの舟だけが漂っている。それまでは街や宇宙といった、いわゆる場所が背景にあるんですけど、3シーン目では、ただただ記憶として漂っているから、すごく寂しいっていう…」
──歌声と合わさって、とても悲しいですよ。もう人類がいない未来のようですし…。
「私も映像を初めて見たときに“悲しい!”ってなりました(笑)。自分たちだけでやっていたらこういう絵にはならなかったと思いますし、すごくいいトライだったと思います」

──“これまで”と“これから”を集約したアルバムが完成して、どんな感想を抱きましたか?
「自分たちはジャンルっていうものを自分たちを意識してやっているんだなっていう発見があったことによって、次のステップに進めるような、自分たちにとっても背中を押してくれるようなアルバムになったと思います」
──“これから”の部分ですけど、“monjeとしての新たな形”は見つかりましたか?
「どうなんでしょう? 振り返ってみると、本当にいろんな曲を作ってきたんですよね。まず、“いろんな挑戦をしてきたんだなぁ”っていうのが、物量として自分たちで確信を持てたのが嬉しかったです。全パターンで曲を作ったんじゃないか?というくらい、いろんな作り方をしてきたっていうのも1つの発見だったんです。歌詞先もあれば、曲先もあって、テーマやコンセプトから作った曲もあります。そこで、自分たちは、改めて、“ものづくりやクリエイティブの1つの手段として音楽があるんだ“ということも認識しました。そういう意味では、音楽以外のところも含めて提示できるようなものになったらいいなと思います。今年は、ものづくりもしていきたいです。”もう少し手を動かしてものを作っていきたい”という気持ちです」
──例えば?
「先日、私たちが作ったマイクスタンドをCENTさんのワンマンライブで使ってもらったんですけど…」
──え!? そのライブに行ってました。ロケットのようなマイクスタンド、特注だよねって思いながら見ていました。
「見に行ってたんですね、すごく嬉しい。あれ、私たちがデザインから制作まで全部やったもので、世界に1つしかないんです。私がデザインして、森山くんが溶接して、3Dプリンターで切って、塗装して。ああいうことをやっていきたいんですよね。他のアーティストさんの世界観の中で、自分たちのクリエイティブを提供できるっていうのは、私たちが目指している“懸け橋”としての役割に近いものづくりなんじゃないかな?と思っていて。それでやってみた結果、“すごく合っているな”って思いました。特に“音楽も内包したものづくりである”っていうところ。ただのものづくりとは全然違って、自分たちも音楽アーティストをやっているからこそ分かる視点があったりするので。それをそのままクリエイティブとして、実際にものとして立ち上げることができるっていうのは、それこそ本当に私たちにしかできないものづくり、クリエイティブになるんじゃないかな?って、ちょっと可能性を感じています」

──音楽が表現の“手段”の1つだとしたら、“目的”は何になりますか?
「この3年間、実際に音楽をやってきた中で、自分たちが今までやってきたアートや美術とは全然違うところに届ける先があったりするのもすごく面白くて。音楽によって伝えられることはすごく大きいです。その発見をしたからこそ、自分たちのフィールドが広げられたような気がしています。多分、音楽をやってなかったら、こんなに多くの人に出会えていないだろうし、それに関しては、私も森山君も音楽が持つ絶大な力を強く感じています。逆に、音楽に力があるからこそ、自分たちが今までいた芸術、美術、アートのフィールドにも絶対に共通するところがもっとあるんじゃないか?っていう疑問も湧いています。どっちのフィールドにもいる身として見えてくるものがたくさんあったと思うんです。その中で音楽を続けていく意味も絶対にあると思っています。音楽でしか出会えない人たちっていうのは本当にたくさんいたので、また新たな出会いをしていきながら、monjeとして、いろんなものと、いろんな人と、いろんなジャンルの架け橋になっていけるのが理想だと思います」

(おわり)
取材・文/永堀アツオ
写真/寺本篤史