
Profile/井上真美(いのうえ・まみ)「miffew」デザイナー
服飾専門学校を卒業後、アパレルメーカーでデザイナーとして服作りに携わる。2015年、ビショップに入社。着る人の所作を美しく見せる丁寧な服作りを特徴とする「WHYTO.(ホワイト)」などのデザインを手掛ける。23-24年秋冬シーズンから「miffew(ミフュー)」のデザイナー。現在はミフューとホワイトのデザインを担う。
ダウンウェアに見えない「驚きのある、あたたかさ」
――ミフューのアイテムはダウンならではの防寒性を備えながら、タウンユースのファッションに落とし込まれています。シャツがダウンだったり、これがダウン?!と驚いたときには、すでにプロダクトに興味が湧いている。
「STAY WARM WITH WONDER~驚きのある、あたたかさ」がコンセプトなんですよ。このコンセプトが生まれたのは、ビショップが展開していたブランドのリブランディングがきっかけでした。2015年に「THE LOFTLABO(ザ ロフトラボ)」という、メイド・イン・ジャパンのダウンウェアブランドを立ち上げたんですね。当時もスポーティーなダウンウェアはたくさんあったんですけど、毎日の生活に十分な最低限の機能があって、年配の方々まで世代を問わずに着られるようなデザインのものはあまりありませんでした。そこで国内有数のダウン専門工場の協力を得て、オーバースペックではない、機能性とデザイン性をバランス良く調和したダウンウェアを提案したんです。

――ザ ロフトラボでもダウンウェアに見えないものを作っていたのですか。
というよりは、表地に撥水加工を施したナイロンを使い、中に国内産のダウンとフェザーをしっかりと入れたダウンウェアで、ステッチをあまり入れないミニマルなデザインが特徴でした。百貨店や専門店に卸していたんですけど、やがて同価格帯で同様なダウンウェアが増えてきて、リブランディングすることになったんですね。結論として、普段の生活の中で着られるファッションとしてのダウンウェアを追求し、一格上のプライスゾーンで展開することになり、新たなブランドとして「ミフュー」を立ち上げたという経緯があります。そのタイミングで私がデザインを担当し、オーセンティックなアイテムで「ダウンに見えないダウン」を作り始めました。
――ミフューになって、都市生活に寄り添うファッションとしてのダウンウェアに特化したのですね。
はい。私自身、ダウンウェアというと、頭のどこかにスポーツやアウトドアの文脈がありました。例えばデートに行くとか、ちょっといいお店に食事に行くとか、子供の授業参観に行くとか、そういうときの選択肢にダウンウェアは入ってこなかったんですね。せっかくダウンを専門に扱うのだから、カジュアルなシーンはもとより、ちょっとフォーマルなシーンの装いの選択肢にも入れてほしい。防寒ができて、ダウンに見えなくて、日常的なスタイリングがしっかりと決まるアウターがあっていいのではないか。そこが出発点となって、ダウンには無かったアイテムを作るようになったんです。

――スポーツ向けやアウトドア向けのようにハイスペックでなくてもいいと。
そこまでは。なので、ミフューのダウンは700フィルパワーは備えているけれど、パンパンになるような量はあえて入れていません。防風素材を使うとか、止水ジップにするなど機能にこだわったダウンウェアも魅力はあるんですけど、私たちが目指しているのは街着としてのダウンウェアなので、そこまでの機能は必要ないんですね。日本の冬を普通にファッションとしてダウンを着て楽しめるようなアイテムを作りたい。ブランド名にもそんな思いを込めています。「miffew(ミフュー)」は、日本の古語である「三冬(みふゆ)」と英語の「few」を掛け合わせた造語です。三冬は旧暦の冬の3カ月間、つまり10月、11月、12月を表しています。fewは「僅かな」の意味があり、限りある資源の中で僅かに採れる羽毛(ダウン)を大切に使っていくという思いを込めました。

オーセンティックなアイテムの魅力を生かす試行錯誤
――ファーストコレクションを発表したとき、バイヤーの反応はいかがでしたか。
「ええーっ!?」という感じでしたね。「シャツにダウンって、どうなってるの!?」って(笑)。私たちが最初に作ったのはシャツだったんですよ。コンセプトに沿って、どんなアイテムにダウンが入っていたら面白いかを挙げていったんです。長く愛されるオーセンティックなアイテムを軸に考えたときに、「シャツなのにダウン」ってすごく面白いんじゃないかと。アウターとして捉えれば長い期間着られるとか、シャツなら洗えたらいいねとか、いろいろ考えながら試作を重ねていきました。試行錯誤して完成させたのが「OVER DOWN SHIRTS(オーバーダウンシャツ)」です。オーバーサイズなのでアウターとして様々なコーディネートを楽しめ、軽量で、インナーにTシャツを着るだけで十分にあたたかい。インナーダウンが要らないんですね。寒くなるにしたがって、Tシャツを半袖から長袖へ、長袖から例えばタートルへ、ニットへと変えていき、マフラーを巻けば、気候にもよりますが12月ぐらいまではカバーできます。ファーストシーズンから売れ筋の一つで、ミフューの「顔」になっているアイテムです。


――ダッフルコートやステンカラーコートもダウンには見えない。どう作るとこうなるのですか。
シャツと同様、昔から愛されているアイテムなので挑戦しました。どうやったらダッフルコートの重厚感を表現できるのか、どうやったらステンカラーコートのすっきりとしたシルエットができるのか、そもそもダウンなのに膨らまないってどうすればいいんだろう……。試作段階では困難を極めましたね。ダッフルの表地はSuper140sの高品質なウールを原料として、僅かにナイロンを混紡したメルトンです。だから軽くて、肌触りも滑らか。そこにダウンを内蔵しているんですけど、重厚感を出すためにパーツごとにダウンの量を変え、厚さを変えた芯を張っているんですね。芯は200種類ほどある中から6種類を選びました。パターン数は40を超え、パーツによっては芯を2枚重ねたり、フラシにしたり。
――ダウンを浮かせているのですか。
そうなんです。フラシはステンカラーコートにも採用しています。表裏を縫い合わせると、ダウンの膨らみと表地の張り感で吊れてラインができてしまうのが、どうしても嫌だったんですね。バックのフレアやベントがしっかり出ていることがステンカラーの魅力であり、それがダウンコートに見えないポイントだと思ったので、あえて浮かせる仕様を選びました。
――工場の職人さんは相当苦労されたのでは?
できるかどうか分からないというところから始まって、本当に試行錯誤でした。「いったい何枚、芯を張るんや」と。でも、そうした製作背景を伝えると、バイヤーさんもお客様も驚きの後に自然と関心を持ち、価格にも納得してくださいます。


日常の中の実感から、1点1点に工夫を凝らす
――ダウンは高品質のものにこだわっていますね。
「NANGA(ナンガ)」や河田フェザーをはじめ、高品質なダウン製品を手掛ける国内メーカーの協力工場で洗浄、精製、仕上げまで徹底して管理されたダウンをはじめ、リサイクルダウンも積極的に使っています。ナンガで作っているダウンウェアは、河田フェザーのリサイクルダウンで作っています。同社の技術力はもとより、工場がある三重県明和町の超軟水で湿度の低い気候のもと洗浄、精製されたダウンは、新品と変わらないクオリティーで、フワフワなんです。
――生地も国内製ですか。
デビュー以来、国産の生地を使ってきましたが、海外でも質の高いものが開発されているので、ミフューの基準を満たせば採用していきたいと考えています。どうしても日本で作りたいプロダクトがある一方、原材料費などの高騰で商品価格がどんどん上がっている中で、お客様にとって優しい価格で届けたいプロダクトもあります。海外の生地もテストして、問題が無ければ使っていくということを今年から始めました。

――1シーズンに何型ぐらい出しているのですか。
ミトンやマフラー、バッグなどの小物も含めて、だいたい20~25型ですね。25年秋冬シーズンではウールのツイードジャケットに挑戦しました。ダウンベストを着なくてもあたたかく、一般的なジャケットよりも長い期間着ることができます。同素材でダウンを入れたパンツも作りました。このパンツの基になったのが、それ以前に発表したチノパンツです。太腿の下までダウンパックが入っていて、スナップで取り外しができるんですよ。暑くなったら外せば普通のチノパンツとして穿け、寒くなったら取り付ける。足元は結構冷えるので、女性はパンツの下に着込んだりしています。そういう実感を大切にして、一つひとつ工夫を凝らして作らせていただいています。


――まだまだ見えないところに工夫がありそうですね。
あります。アウターって襟が汚れがちですよね。襟が汚れていると、脱ぎたくないし、見られたくない。なので、襟裏に取り外せる汗除けパーツを付属させているんです。シャツやコートなど、取り付け可能なアイテムに付けています。
――きものの半襟みたいですね。
汚れてほしくないところは汚さない、ということです。また、ダウンウェアはそうそう洗えないじゃないですか。このパーツがあることで、本体を毎回洗濯しなくてもよくなります。シャツは丸洗いできるようにしていますが、ダウンウェアですから、できれば春夏に洗いたいですよね。シーズン中はパーツを洗って、清潔に保って気持ち良く着ていただきたい。ミフューの商品は価格が安いものではないので、大切に長く着てほしいという思いがあります。

卸をベースにファンを増やす。年内にECサイトもスタート
――どのような客層がミフューの商品を購入しているのでしょう。
全体としては女性のお客様が7~8割です。ただ、コレクションの8割はジェンダーを意識せずに作っていて、卸先はメンズに強いお店もあれば、ウィメンズのお店もあります。バイヤーさんに聞くと、男性のお客様は若い人から40、50代アッパーなど幅広いようです。女性のお客様は30~40代が中心で、ターゲットが20~30代のお店では若い人たちも購入しています。
――女性客が多いとはいえ、男性客も購入している。サイズ展開はどのようにしているのですか。
1から4までで、2と3の差を大きくしています。1と2がウィメンズ、3と4がメンズのイメージです。でも実際は、私もそうですが3を女性が着ることもあり、2を男性が着ることもあります。ジェンダーに関係なく、好きなサイズ感のものを選んでいただければと思っています。ユニセックスで着られるアイテムが多いのですが、女性のお客様が多いのでフェミニンなデザインのものも作っていて、そういうものは1と2のみで展開しています。

――販売チャネルはセレクトショップが多いようですが、ミフューの商品は現在、どこに行けば買えるのですか。
弊社の他ブランドと同様、ミフューも卸がメインです。大手や各地のセレクトショップを中心に、オンラインのセレクトショップにも卸しています。少しずつですが取引先様の店舗でポップアップストアも展開し、お客様とコミュニケーションしながらブランドの背景を伝えています。
――卸がメインということは、展示会をベースに受注している。
そうですね。三冬のためのダウンウェアなので、新作は年に1回、秋冬コレクションとして発表しています。12月にミフュー単独の展示会で受注し、翌年の秋冬に店頭に並ぶという流れです。25-26年秋冬シーズンに関しては、今年1月にビショップの他ブランドとの合同展も行いました。今年も12月に26-27年秋冬コレクションを発表します。

――ECサイトでの直販はしていないのですか。
ブランドの立ち上げ時から話はあるのですが、正直、服作りの試行錯誤が多く、準備が追いつかない状況でした。オンラインモールには出店しているんですけど、ブランドの世界観を表現できないというか、ミフューのブランディングには合っていないのではないかと思うようになったんですね。であれば、しっかりとした自分たちのECサイトを作ろうということで、ようやく今年中にスタートできる目途が立ちました。実際、お客様からは「このアイテムはどこで買えるの?」と尋ねられることが多いんですね。セレクトショップは自店に合ったアイテムをセレクトするので、お店を紹介してもそのお客様が欲しいアイテムが無いこともあります。シーズンコレクションが全て揃っているECサイトを開設し、お客様が「選べる」環境を整えていきたい。

――今後の展開について聞かせてください。
出店は考えていなくて、あくまで卸をベースにしながら、ECでもブランドの価値を発信していく考えです。物作りに関しては、パターンや生産管理などのスタッフ、得意分野を生かしながら工夫を重ねてくださる工場にも恵まれていると実感しています。ミフューのためなら頑張ろうと思ってくれる素敵な人たちがいることで、私も頑張ろうと思える。そういうことの積み重ねでチームとして動けるようになり、3シーズン目を迎え、4シーズン目に入ります。雑誌社やPR会社の力もお借りして様々な媒体に掲載され、スタイリストさんなどにも見ていただけるようになって、ちょっとずつ認知が広がってきています。これからも着実にブランディングを進め、「驚き」を届けていきたいですね。
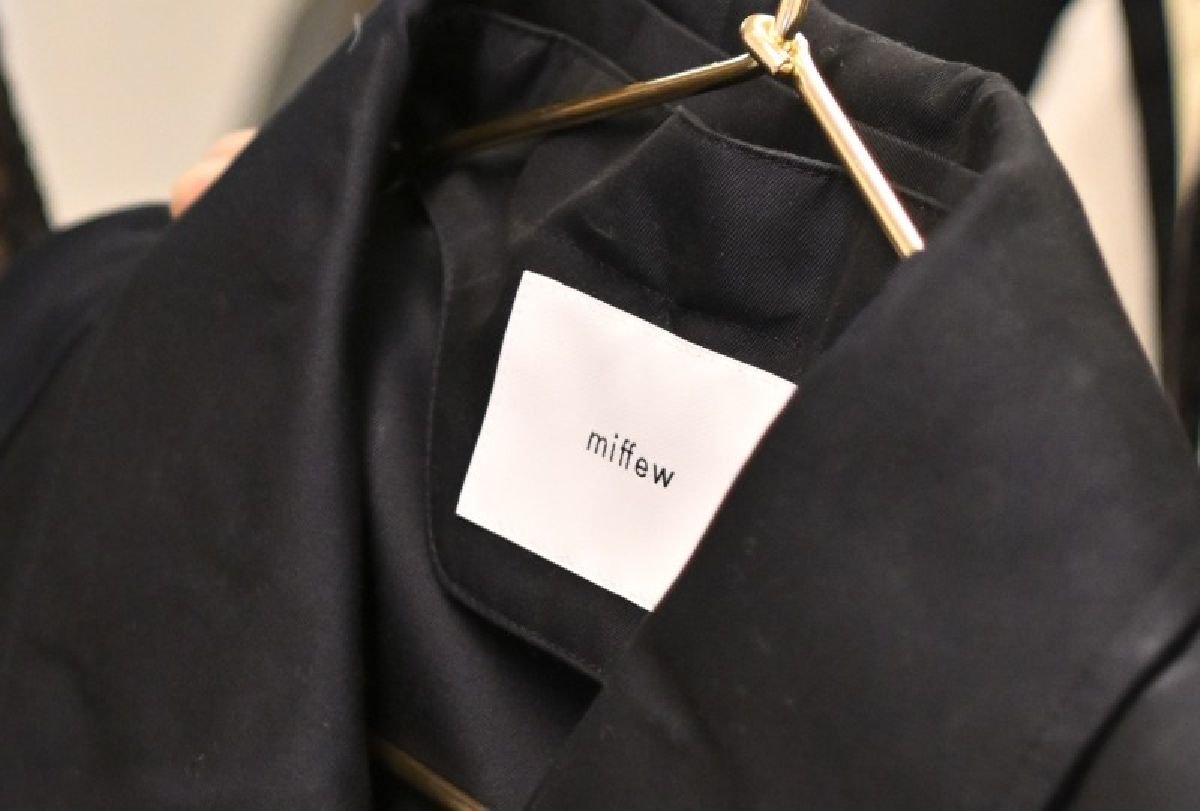
写真/遠藤純、ビショップ提供
取材・文/久保雅裕
関連リンク

久保雅裕(くぼ まさひろ)encoremodeコントリビューティングエディター。ウェブサイト「Journal Cubocci(ジュルナル・クボッチ)」編集長。元杉野服飾大学特任教授。東京ファッションデザイナー協議会 代表理事・議長。繊研新聞社在籍時にフリーペーパー「senken h(センケン アッシュ)」を創刊。同誌編集長、パリ支局長などを歴任し、現在はフリージャーナリスト。コンサルティング、マーケティングも手掛ける。2019年、encoremodeコントリビューティングエディターに就任。




