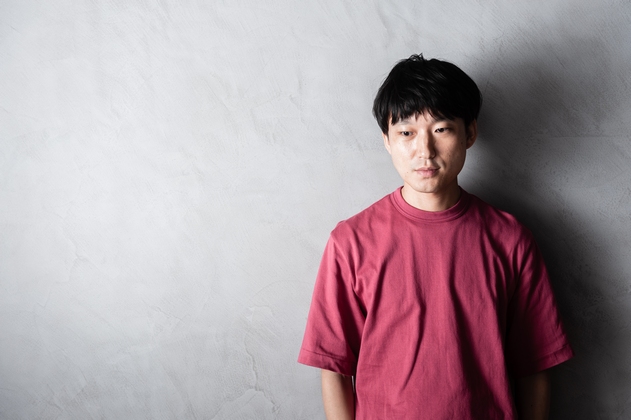<PR>
RADWIMPS、サブスク解禁! by SMART USEN
――『フルフォニー』のアートワークは横尾忠則さんが手掛けてらっしゃいます。作品のコンセプトにマッチしたものだと思うんですが、なぜ横尾さんにお願いしようと考えたんでしょうか?
「リミックス以外の収録曲をレコーディングしたのは1年以上前なんですけれど、それを終えてアートワークをどうするか考えたときに、直感的に横尾忠則さんにお願いしたいと思ったんです。そもそも蓮沼執太フィルのジャケットはずっと絵画なんですよね。ファーストアルバムの『時が奏でる』は光る山で、セカンドの『アントロポセン』は飛行機の窓から見た風景が描かれている。人間が登場しない風景画であることにも暗黙のコンセプトがあって。で、今回のジャケットは横尾さんが70年代に日本を旅行して風景画を描いていたシリーズがもとになっていて、僕もそれを以前に展覧会で見ていたんです。あの絵は北海道の大沼と駒ケ岳だけで、人間もいなくて、それぞれの生物や自然が共生している感じがある。それぞれが存在している感じというのが、僕がフィルでやりたい感覚と近いと思っていた。そういったところから考えて、横尾さんにお願いしようと思いました」
――蓮沼執太フルフィルの初演は2018年夏のすみだトリフォニーホールでしたが、26人編成のアイディアはいつ頃からあったんでしょうか?
「フィルでのファーストアルバムを出した後に僕がNYに行ったんで、フィルをやっていない時期が1、2年続いたんですね。それで数年ぶりにライブをしたのが2017年2月の青山スパイラルホールの2デイズでした。それが終わったあとにメンバーにこのアイディアを言いました。そこから徐々に組み立てて、公募という形でメンバーを集めていきました」
――蓮沼執太フィルが16名で、フルフィルはそこに10名が加わった編成ですが、それぞれ関係性は違いますか?
「これは全然違いますね。僕は合奏するときに、お互いの信頼関係がないとできないし、楽しくなきゃアンサンブルをやっている意味がないと思うんです。いきなり新しい人が10人来ても急に全て通じ合えるわけではないんで、やっぱりその差は大きい。僕は16人を「フィル」、10人を「フル」と呼んでますけれど、フィルのみんなはそれぞれのフィールドで独立した形で音楽活動をしている一方、フルの人たちは別の仕事をしながら音楽をやっている人も多い。そういった環境の違いもありますね」
――蓮沼執太フィルにしても、蓮沼執太フルフィルにしても、大前提としてシンフォニック・ポップの新たなあり方を開拓していると思うんですね。オーケストラ編成の音楽は、基本的には指揮者のもとに構成されたトップダウン的な調和によって成り立っていると思うんですけれど、それとは違って中央集権的というよりも、1人1人にオーダーメイドなものが与えられていて16人のフィル、26人のフルフィルになっている感じがあるんです。
「ファーストアルバムに至るまでの初期の活動は僕がヘッドアレンジを決めて、集合知的な、みんなの意見を束ねながら作っていくというスタイルでした。『アントロポセン』のときはメンバーも固定なので、メンバーのためにフレーズを作っていくという経緯もあって。なので、中央集権的なトップダウンのオーケストラという形ではなく、全員が同じフラットなところに立っているという作り方は、ベーシックにある大切な要素だと思っています。と言っても、それだけが僕のやり方というわけではない。コンセプトというよりは、みんなといっしょにやっていくひとつの方法みたいな感じです」
――フィルやフルフィルの活動は、傍から見ていると“合奏をする”とか“アンサンブルで音を鳴らす”という行為を、プログラム言語のレベルから作り直しているという感じがするんです。これは相当に大変なことなんじゃないかと思うんですが。
「大変ですよ(笑)。でもそう言っていてもしょうがないので噛み砕いていかないといけないんですけれど。自分たちの音楽を他人のフォームを借りずにやって、さらに人間関係のあり方もオリジナルで構築していく。しかもインディペンデントでやっているので、そういう感覚でやっていくのは、正直、大変です。けれど、僕は新しいこと、聴いたことのないサウンドを追い求めて音楽をしている人間なので。そういう姿勢と他者と一緒に音楽をするということの探究心は同じ気がしていますね。音を鳴らす道具をゼロから作って今までに聴いたことのない音を作るというチャレンジにニュアンスとしては近いと思います。それを人と人との関係性で合奏として作っているというか」
――ちなみに“自分も蓮沼執太みたいなことがやりたい”という人、10数人を集めてオリジナルなアンサンブルを作りたいという人がいたとして、どんなアドバイスをしますか?
「止めたほうがいいよって言います(笑)。まあ、それは言うけれど、いろんな人が集まって何かひとつのことをやるというのは、音楽だけじゃなく社会にはいくらでもありますからね。建築だってそうだし、ラボもそう。ジャンルは違えど、アートでも集団で何かをやるということで生まれてくる差異や共通項に興味はあります」
――初演のすみだトリフォニーの時を振り返っていただいて、あれが終わったときの感触はどんなものでしたか?
「僕、いつもそうなんですけれど、だいたい最初は失敗するんですよね(笑)。さすがに人数も多いし。頑張るんですけれど、いつも“もっとできたな”と思う。あの時もそういう感じでした。まだまだできると思ったのが正直なところですね」
――あのステージを観ていた側の印象としては、すごくフェスっぽい感じがあったんです。ばらばらなところから始まって、最終的にはとても祝祭感のある体験だった。蓮沼さんも“まだまだできる”と思ったということは、おそらくあそこで掴んだ手応えが大きかったんじゃないかと思うんですけれど。
「僕の作家性でもあるんですけれど、失敗をネガティブに捉えていないんですね。コンダクターがしっかりとコントロールするというのが既存のアンサンブルの形だと思うんですけれど、それって楽器や身体のコンディションの違うみんなを束ねて、整えてひとつの時間の中で音楽にするということで。それと違って、ああいう空間で僕らみたいなアンサンブルが演奏すると、普段とは違った響き方になる。それを統率しないといけないというか。さらに新しい形を作り出さないといけないんだなと思いました」
――そこからツアーやフェスなどでフィルの公演を重ねていったわけですが、楽曲はどういうふうに育っていきましたか?
「今回のアルバムに収録されている楽曲は、実はフィルでも全然できるんです。それで、すみだトリフォニーホールが終わったあとに『アントロポセン』のツアーもしていたんですけれど、そのツアー中にどんどんコンディションがよくなっていったんです。どんどん慣れて、楽曲が身体化していくんですね。それだけでなく、数年前に第一期としてやっていたフィルとは違う感じになっていて、歳を重ねてメンバーの個性がさらに生まれてきている。たとえばスティールパンの小林うてなはblack boboiというバンドをやっていたり、自分でレーベルをやっていたりもする。そういう新しい手応えがあったんです。そうやってフィルの基盤が固くなった中にフルの人たちが入ることによって、みんなの中で楽曲が自分の一部になっている感じがあって。よくなってましたね。バンド感が出てくる感じはありました」
――レコーディングするときにはどういう考えがあったんでしょうか。
「いままでの作品も全部同じなんですけれど、フィルって、一発録りなんですよ。スタジオに入って、セクションごとにブースに入って、せーので録る。でも26人だと入り切らないので分けるしかない。だから最初にフィルで録って、その後にフルに来てもらって録音しました。レコーディングをするというのは、基本的には記録をしていく、という感覚ですね。最近は立体音響のワークショップに参加していたりもするんで、正直言うと“まだ2チャンネルで作るんだ……”っていう気持ちもありますけれど。なんせフルフィルは音が多いからたくさん出力があったほうがいいに決まってますし。だけど、音盤に焼き付けて楽しむという歴史もあるし、その文脈の中でどう面白いことを発見できるかを追い求めているというのはありますね」
――『FULLPHONY』では、フィルとフルフィルの違いはどういうところに出てきましたか?
「より非音楽の要素が増えたようには思いますね。電子デバイスを扱うメンバーが増えたということもあるんですけれど、さらにバラバラにするというときもあれば、塊のように一つにするのもできるようになったと思います。というのは、『FULLPHONY』の第1楽章は、プレイヤー一人ひとりが自分の脈拍を測って、そのテンポで僕が作ったフレーズを弾いていく。全員バラバラなところから立ち上がっていくんですね。そこから曲が進行していくにつれて、一つになったり、またバラバラになる。そういうコンポジションにしてあるんです。フィルというのは、編成のせいもあってそこまで粒が細かくはならないけれど、フルの場合はより分散的になるし、ギュッと固まったコンポジションのときにはより凝縮する。その差が大きくて、レンジが広いという感覚はありますね。
――『FULLPHONY』の協奏曲としての構成はどういう風に作っていったんでしょうか?
最初に第1楽章の脈を測るところから順番に作っていったんです。ニューヨークにいたんで、ずっと部屋で外を眺めながら考えて作っていったんですけれど。これまでフィルの音楽は映像的な作り方はあえて避けていたんですけれど、今回の『FULLPHONY』ではそういうところはありますね。第2楽章のスローなテンポでヴォーカルが入って広がっていく感じというのは、まさに横尾忠則さんのジャケットのイメージなんですね。全てが活き活きしている環世界があるというイメージで作っていった感じです。第3楽章は全員が顔を出すような展開だったので、より制限をして、ミニマルにしていくことで縦のラインを揃えている。バラバラなものを縦で刻んでいくことで一つにしたかったというのはありますね。第4楽章は5拍子でラップとヴォーカルが入っているという、あまりポップスの世界にはあまりない試みをしていて。そういったものも試したかったというのもあるし、アンサンブルの熱量というのを形にしたかったというのもあります。全員が盛り上がっている熱さを最後に出したかった。それもこれまでのフィルの曲作りだとあまりなかったことですね」
――「windandwindows」は全く別のモチーフですよね。
「「windandwindows」は前から作っていた曲ですね。「風と窓」というタイトルで、風が抜けるような曲になればいいというイメージもあった。これは純粋に合奏を楽しめる曲になるんじゃないかと思って、フルフィル用にアレンジして歌詞も書いたという曲です」
――アルバムにはそれぞれのリミックスが収録されていますが、この構成はどういうところから考えたんでしょうか。
「自然とこうなったという感じはありますね。レコーディングしてから時間が経って、リミックスしたのが、ちょうどコロナ禍で自粛ムードになってからで。社会の状況が変わっていくなかで、フルフィルの曲を自分で扱い直すというのは、自分の現在地を知るためにもいいかなと思ってやった試みです。大人数で作ったアンサンブルを自分のフィルターを通して形にしたときにどうなるのかという。接触もできない世の中になったわけですけれど、フルフィルはまさに接触しているわけで、そういった対比も出ると思いましたし。26人で作った楽曲に対して違った視点を作ることで、また違うことを発見できるというのもあるし。理由は複合的なんですけど、やってよかったです」
――確かにコロナウイルス禍のせいで世界的に人と集まりづらい状況になっている。フルフォニーみたいな表現は、いま現実にやろうとしたらいちばん難しいですよね。そういう意味でも、合奏というものを対象化する経験だったんじゃないかと思います
「そうですね。普通だったらレコーディングしたらすぐ出すんですけれど、それが時間があいて、今出すことになった。そのことで、俯瞰的に見ることもできたし、合奏とは何だったんだということも考えることができた。それは不思議な体験で。そうなったのは何かの縁もあるだろうし、新しい気付きを発見できたとは思います。やっぱり作ってからアウトプットされるまでの2、3年の社会の動きは作品に密接に反映されていると思いますね」
――8月29日には蓮沼執太フィルのオンライン公演「#フィルAPIスパイラル」が開催されます。これはどういうものをイメージしていますか?
「これはアルバム収録曲を中心に蓮沼執太フィルでやるんですけれど、ゲストを考えていて。RYUTistにも来てもらって、RYUTistに提供した曲もやろうと思っています。去年にやった日比谷野外音楽堂がいい区切りだったんで、次の段階に向かうためのデビュー戦という感じですね。新しいものになると思います」
(おわり)
取材・文/柴 那典
写真/いのうえようへい
■蓮沼執太フィル オンライン公演 #フィルAPIスパイラル
ZAIKO
8月29日(土)19:00配信 ※アーカイブ視聴は9月5日まで

- 蓮沼執太フルフィル『フルフォニー』
-
2020年10月28日(水)発売
完全予約限定生産盤(CD+BOOK)/POCS-23906/8,000円(税別)
Caroline International