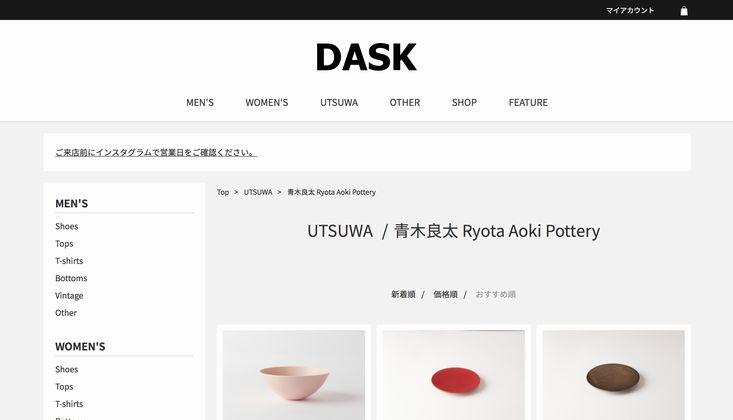<PR>
「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」by SMART USEN
[section heading="ゲストスピーカー"]
[section heading="自分が心から良いと思うものを提案できるお店があったら面白いと思った。"]
――お店を始めたきっかけを教えてください。
「ファッションが好きで、ずっとこの業界に関わる仕事をしています。好きなものを提案し、それがお客様に受け入れられ、会社がどんどん大きくなっていく。その感覚は前職でもダイレクトに感じていたので、とても楽しかったです。ただ、ビジネスとして大切なことではありますが、時代とともに、心からおすすめできるものじゃないスタイルやお客様志向に寄り過ぎていくことに、少しずつ違和感を覚え始めたことがきっかけです。なにか物足りないようなもどかしさは、数年間続きましたね」
――それがきっかけとなって自分のお店をスタートしたわけですね。
「音楽やスケートカルチャーだけでなく、ここ4?5年、和食器に興味を持ち始めて、個人的に作家さんのものを買って使っていました。もし自分でやるのなら、心から良いと思うものを提案できるお店にしたいと思って。今まで経験があるファッションではない分野の和食器をあえて軸にして、そこに自分の培った経験やカルチャーを混ぜたらどうなるのだろうとか、ある程度想像はしていましたね。当初は、自分でお店をやるつもりはなかったのですが、とあるきっかけでオープンすることに。自分が好きと思えるものは、きっとお客さんに伝わるという想いは根っこにありましたし、その気持ちを大切にしていきたい。これが売れるから、とかではなく思い入れがあるものや自分が詳しいもの、紹介したいもの、その思いが強いかどうか」
――和食器をセレクトする際のポイントはどこですか。
「今は20名前後の作家さんにアプローチしています。笠間が一番多く、益子、岐阜の土岐、愛知の常滑、半田。関東圏が多いですが、一部九州のものも仕入れています。陶器だけでなく、陶磁器、木工、硝子、スリップウェアの器まで。こういった料理に合いますよ、といった実用的な視点というよりは、ひとつの造形物として見ています。横から見たシルエットや質感がかっこいいものがたくさんあるので、眺めるだけでも楽しめるようなセレクトで、あとは全体のバランスを見ながら調整をしています。それは、どこか洋服を見ている感覚に近い選び方かもしれないですね。日常使いできるものもあるけれど、奇抜な器も多いです。"いつかこの器に合う料理を作る"といったスタイルを提案しています」
――和食器が軸、という発想は面白いですね。ほかの仕入れのことも教えてください。
「和食器をベースに、自分の好きなミリタリーやアウトドア、ストリートテイストを掛け合わせています。個人商店なので、世界初のブランドを取り扱っているといったニュース性よりも、自分が変わらずに好きで納得できるものだけを置いています。中でも手に入りにくいビンテージや古いデザイナーズものなどには重きを置いていますね。靴は95%以上が"ヴァンズ"です。レディス、メンズ関係なく、すべてアメリカ企画。ウェアに関しては、デットストックのアメリカ軍のスノーパーカーをカスタムして売っています。ベージュに染めてから後ろ布を抜いてドローコードも付けています。10枚ぐらいありましたが、あっという間に売れてしまい、残り1枚。"よりこうなったらかっこいいかも"というインスピレーションをダスクのオリジナルとして提案をしています。良いと思ったものがたまたまユーズドだったり、新品だったり。あくまで、自分の視点によるセレクトですが、自分のフィルターを信じながらバランスだけは考えています」
[section heading="和食器とファッションのミックスは、僕なりの「概念」への解釈。"]
――ご自身がファッションに目覚めた時期はいつでしたか。
「小学校のときですかね。自分が選ぶ服を着たいという意識が芽生えたのは、5年生くらい。親が選ぶ服はとにかく嫌で、一緒に買いに行っていました。中学生になると、当時2,800円くらいのコンバースのオールスターを履いていて、色違いの赤白黒を揃えたりしていましたね。高校時代は、ギリギリDCブームがあって、その後アメカジの流れでラルフローレンやリーバイスが好きになりました。そこが思えば、今のルーツでしょうか。 高校卒業後は、ファッションではなく、ビジネスを学びました。音楽ライターを目指したこともあって出版社に就職し、そこでは、音楽とは違うジャンルでしたが編集者として2年半ほど務めました。その後ファッション業界に入り、当時ヴァンズの代理店で運良くウェアのアシスタントバイヤーを経験しました。その後、とあるセレクトショップが東京に進出したという話しを聞いて、その店舗を見に行きました。その店舗が前職のセレクトショップなのですが、とにかくかっこ良かった。本社勤務ではなく、渋谷店の販売スタッフからでしたが、ここだったらそれでも良いと思って入社しました」
――前職で学んだことは大きかったですか。
「人との付き合いですかね。それは、お客様、チームの仲間や取引先の方々。"モノ"で売れていた時代ではありましたけど、やはり"人"だったとも思います。また、違うフィールドのアイテムやブランドを組み合わせたセレクトショップの概念はここで学びました。今やっていることに近いのですが、"オールデン"の靴と1,900円の"ヘルスニット"のTシャツと古着が並んでいるお店は、当時あまりなかったのです。それに店頭のBGMはジャズで、什器はフランスのデザイナーの"ジャン・プルーヴェ"風。とにかくいろいろなテイストが混ざっていて、強く惹かれました。それらはダスクに繋がっていますし、和食器とファッションのミックスは、僕なりの"概念"への解釈です」
――ステレオタイプにはまらない、新しい価値を生むということですね。
「組み合わせの妙みたいなものは学びましたね。"新しい価値観を生む"。パッケージにして新しい世界を提案していきたい。」
[section heading="儲かる、儲からないじゃなくて、楽しいイベントをやっていきたい。"]
――去年の12月にオープンしてから一年ですね。
「最近このエリアも賑わってはいますが、やはりメインからは少し離れたところにはなるので、未だに"いつできたの?"と聞かれます(笑)。でも、まだ知れ渡ってないということは、プラスに捉えています。お客さんは、地元というか世田谷エリア全般から来てくれます。年代は30~40代の層が多くて、自分が通ってきた音楽やファッション、スタイルに共感してくれる方が多い。子供連れのご家族も多く、旦那さんがヴァンズを買って、奥さんは食器を買うということもよくあります」
――今後の課題はありますか。
「自分が前に出て行くことですかね(笑)。"たくさんの方に知っていただくような活動はしていかなくては"と考えています。多くのお客さんに"もう買うものないや"と言われたら諦めが尽きますが、まだこのお店を知らない人もいるのだったら、知ってもらうように続けていきたい。正直、常連のお客さんには"メジャーになってほしくない"ってめちゃくちゃ言われますけど(笑)」
――ECでファンを増やしていくことも考えますか。
「そうですね。ちょうど最近始めたところです。お店の良さは、ウェブサイトやインスタグラムを通してでも伝えられると思っています。皆さん忙しいですから、そういった時間がない方のために、お店のことをわかってもらえるひとつのツールとして、ECにも力を入れて紹介していきたいと思っています」
――来年、2020年のチャレンジを聞かせてください。
「儲かる、儲からないじゃなくて、楽しいイベントをやっていきたいです。知り合いのスタイリストダスクの看板を書いていただいているイラストレーターの安部竜一さんとも近々面白いことを計画しています。洋服もアートも、和食器もジャンルは問わず、ともに楽しんでもらえるような企画を考えていきたいです。PRでも"この商品が入荷しました"というアナウンスよりもイベント自体を宣伝していきたいですね」
[section heading="サマリー"]
オーナー佐藤さん自身がリノベーションしたという2フロアの店内には、和食器のほか、デッドストックのヴァンズに"ヘルムートラング"の年代もののアウターやレコード、アウトドアブランドまでが並び、畳にはスケートデッキがディスプレイされていた。和テイストをモダナイズしていて、遊び心に溢れたセレクトなのにどこか落ち着いた印象。そのすべてには完成された統一感があり、洗練されたものばかりが並んでいた。長年ファッション業界で培ってきたセンスが導く提案には、どこか間違いないと思える安心感がある。佐藤さん直々にそのモノの良さを教えてもらえるという点こそ実店舗の素晴らしさ。ご自身のことを「クールだねとよく言われますが、話すとフランクなんです(笑)」という通り、丁寧でやわらかい人柄も魅力的。来年は、面白いイベントも予定しているらしく、今後も注目していきたい。
(おわり)
取材/久保雅裕(encoremodeコントリビューティングエディター)
文・写真/成清麻衣子