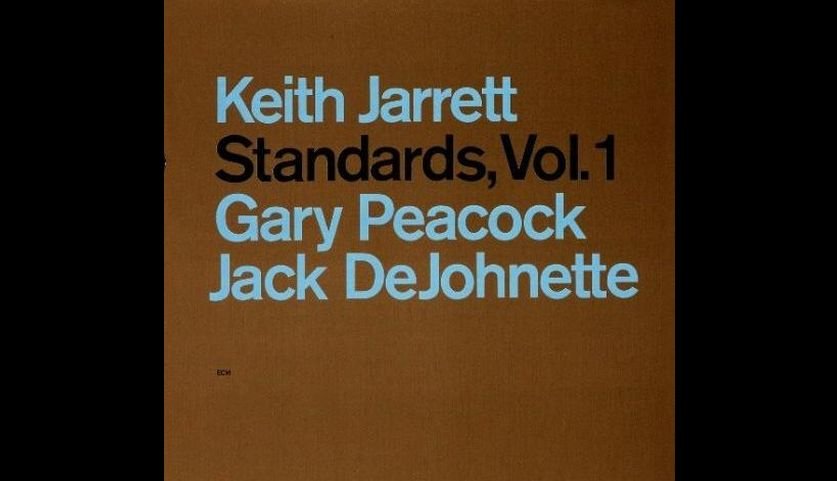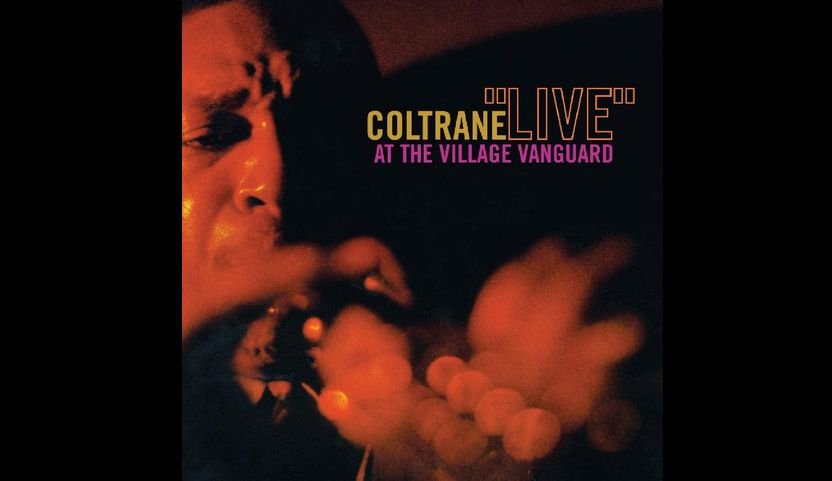現代ジャズピアニストに大きな影響を与え、今も大きな人気を誇るキース・ジャレットは、1960年代にテナー・サックス奏者、チャールス・ロイドのサイドマンとしてデビューした。ロイドの『ドリーム・ウィーヴァー』(Atlantic)でのキースは、それまでのジャズピアニストとは明らかに発想の違う斬新な感覚でファンに注目され、また、このロイドのアルバムでキースは、後にチームを組むことになるドラマー、ジャック・デジョネットと出会っている。キースのスタート地点を知るに欠かせない作品だ。
その後キースは2枚のリーダー作を吹き込むが、3作目にあたる『サムウエア・ビフォー』(Voltex)でボブ・ディランの《マイ・バック・ペイジ》を取り上げ、ロック世代のジャズピアニストであることを印象付ける。そして71年に吹き込んだ画期的なソロ・アルバム『フェイシング・ユー』(ECM)で、新世代ピアニストとしての地位を確固たるものとすると同時に、チック・コリアと共に70年代ソロピアノ・ブームの先駆けとなる。
70年代以降キース・ジャレットは、サイドにテナーのデューイ・レッドマンを従えた、いわゆる「アメリカン・カルテット」と、ヨーロッパのミュージシャン、ヤン・ガルバレクをサイドとした「ヨーロピアン・カルテット」の二つのグループで演奏活動を行ってきたが、『宝島』(Impulse)は、アメリカン・カルテットのメンバーにギターとパーカッションが加わった楽しいアルバム。
一方、同じ年に出たヨーロピアン・カルテット『ビロンギング』(ECM)では、独自の個性的サウンドを持ったガルバレクのテナー、ソプラノ・サックスが人気を呼んだ。『生と死の幻想』(Atlantic)は編成としてはアメリカン・カルテットだが、チャーリー・ヘイデンのベースとのデュオで演奏された《祈り》がキースのリリックな面を捉え、大変素晴らしい。
70年代、キースは大量のソロ・アルバムを発表し、どの作品も即興演奏の新たな可能性を切り拓いた斬新な傑作だったが、中でも『ステアケース』(ECM)はキースの即興の素晴らしさと旋律の美しさが際立った名演。ヨーロピアン・カルテットの2作目である『マイ・ソング』(ECM)は、キースのロマンチックなメロディメーカーとしての資質が人気を呼んだ。それにしても、同じカルテット編成でも、デューイ・レッドマンのアメリカン・カルテットとはずいぶん雰囲気が違う。こうした異なる性格を持ったメンバー達と同時に活動できるのは、キースの音楽性の幅広さを示すものだろう。
70年代、ソロ、二つのカルテット、そしてクラッシク的アプローチの作品など、極めて多彩な音楽性を見せたキースだが、それらはほとんどがオリジナル作品であった。そのキースが、80年代に入ると突如としてスタンダード・ナンバーを取り上げるためのグループ「スタンダーズ・トリオ」をゲイリー・ピーコック、ジャック・デジョネットと結成し、ファンの意表を突いた。『スタンダーズ第1集』(ECM)は、その後おびただしい数のスタンダーズ・シリーズを出すこととなったトリオ編成の記念すべき第1作で、当時流行した予定調和的スタンダード演奏に対する批判を込めた、極めて意欲的な演奏。以後、多くのピアノトリオ・グループが彼らの緊密な演奏を手本とした。
80年代から90年代かけ旺盛な演奏活動を展開したキースだが、慢性疲労症候群という病気に罹り、しばらく演奏活動の中断を余儀なくされた。『ザ・メロディ・アット・ナイト・ウイズ・ユー』(ECM)は、病が回復した後の演奏で、それまでの鋭さは消えたが、その代りに、音楽に対する深い愛情が聴くものの心を捉えるしっとりとしたわいがキースの新境地を示している。
文/後藤雅洋(ジャズ喫茶いーぐる)

USEN音楽配信サービス 「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」
東京・四谷にある老舗ジャズ喫茶いーぐるのスピーカーから流れる音をそのままに、店主でありジャズ評論家としても著名な後藤雅洋自身が選ぶ硬派なジャズをお届けしているUSENの音楽配信サービス「ジャズ喫茶いーぐる (後藤雅洋)(D51)」。毎夜22:00~24:00のコーナー「ジャズ喫茶いーぐるのジャズ入門」は、ビギナーからマニアまでが楽しめるテーマ設定でジャズの魅力をお届けしている。