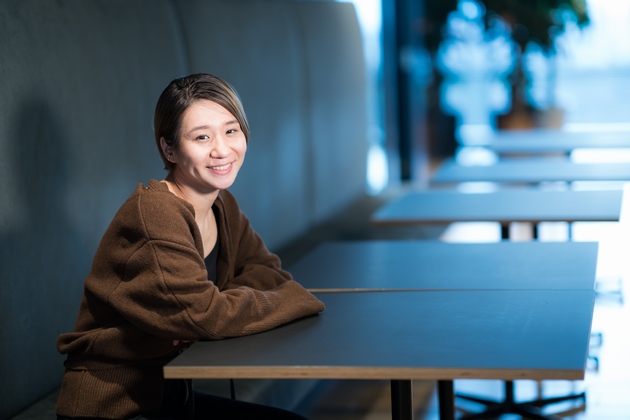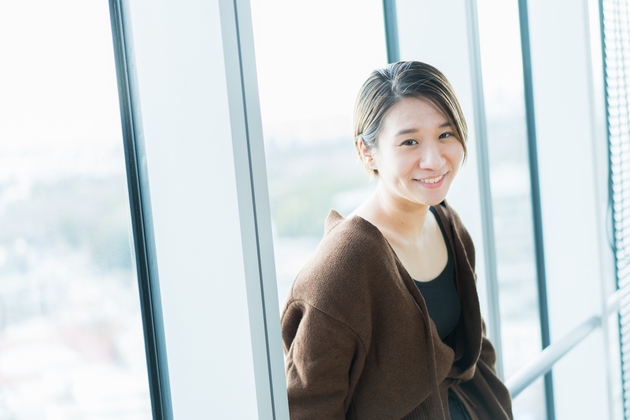<PR>
J-POPフリークの音楽アプリ「SMART USEN」
――『Opera』は桑原さん初のソロ・ピアノ・アルバムです。これまではさまざまなゲストを迎えての作品をリリースしてきたわけですが、デビュー9年目のタイミングでソロ作品を作ることになったいきさつを教えてください。
「私はもともとエレクトーン出身で、ピアノに転向したのが中2だったんですけど、そのときにエレクトーンとピアノがあまりにも違い過ぎて、まったく弾けない自分に絶望してしまって。そこからピアノ人生がスタートしていることもあって、ピアノに対するコンプレックスがずっとあったんですよね。21歳でデビューしてからも、どれだけ練習しても自分の思う音が鳴らないとか、やっぱりジレンマを抱えていたんです。一時はエレクトーン出身であることを言うのもイヤだと思うほど、自分の過去をすごく悔やんだこともありました」
――“悔やんだことがあった”と過去形で話されたのには、そこから抜け出すきっかけがあったんですか?
「私が14歳のときからついている、クラシックピアノの先生の存在が大きいですね。本当にその先生が良くしてくださって。弾き過ぎて腱を痛めたり、筋力が足りない状態でここまで来てしまっていることを踏まえ、私にしか鳴らせない音を出すこと、いかにピアノの芯をとらえた音を鳴らすかというところにフォーカスしたレッスンをしてくださいました。ピアノって、いくら力づくで弾いたところで、ただ大きな音になるだけで音が鳴ってるとは言えないんですね。そこで先生は私に、身体を作るところ、ピアノの弦を鳴らすための身体の使い方といったようなところから丁寧に教えてくださいました。以前から、自分の音が鳴らせるようになったらピアノのソロアルバムを出したい、30歳でそこに近付けていたらいいなと思っていたんですけど、25、6歳までは鳴れ!鳴れ!って感じで、本当にピアノと喧嘩しているみたいな感覚でしたね。でも、少しずつレッスンが実を結んだのか、27歳頃からピアノに対して自信を持てるようになってきて。そうしたら29歳になるちょっと手前で会社からソロアルバムの話をもらい、今がそのタイミングなんだなと思ってありがたく受けさせていただきました」
――収録曲の中にはシシド・カフカさん、立川志の輔さん、山崎育三郎さん、社長(SOIL&“PIMP”SESSOPNS)さん、平野啓一郎さんが選んだ楽曲がありますが、意外な選曲や、ちょっと難しそうと思った楽曲はありますか?
「シシド・カフカさんが選んでくださった、ボンジョヴィの「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」と、山崎育三郎さん選曲の「星影のエール」かな。正直、マジかよ!?って思いました(笑)。「星影のエール」は育さんも出られていた朝ドラ「エール」の主題曲だったので、選んでくださり光栄でした。でも私、邦楽をカバーするのが初めてで。アレンジをするのにアプローチの仕方はどうしようって悩みました。そこで参考にさせていただいたのが、小曽根真さんがAIさんの「Story」をソロで弾かれたときのアレンジ。「Story」ももともとメロディが素晴らしい楽曲なので、そこを大切しながら原曲をリハーモナイズするのかと思ったら、意外とシンプルに弾かれていて、なおかつ原曲の良さがさらに引き立つアレンジになっているのを聴いて、さすが、小曽根さん!って感動したんです。それで、「星影のエール」も原曲の良さが伝わるように弾きたいなと思ったのですが、「星影のエール」の場合、原曲のグルーヴ感をそのままピアノで表現してしまうとちょっと浮くというか、ピアノで弾く意味がなくなってしまったんですよね。なので、原曲では3連符になっている部分を8分の6拍子に落とし込み、ハネはしないんだけど、ワルツっぽく踊っている感じのグルーヴにしてみたところ、これならピアノに合いそうと思えるものができたので、メロディは原曲を活かしつつ、リズムでバランスをとりながらアレンジしていきました」
――そして、ボンジョヴィの「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」がリクエストされたときも驚いた、と。
「カフカさんがボンジョヴィを好きなことは知っていたので、予想はしていました(笑)。もしやりにくかったら変えますというメッセージもいただいたんですけど、最初に出してもらったものが一番いいので。自分だったら絶対に選ばない曲です(笑)。ピアノで弾きやすい曲では決してないんですけど、敢えてそれに挑戦するのもいいかなって。やると決めたからには、どうやってでもピアノに落とし込んでみせるっていう、謎の意地でアレンジしました(笑)」
――ひとつ気になることがあるんですけど、アレンジをするときって原曲の譜面を見たりするんですか?
「譜面は見ないですね。とにかく曲を聴きます。コードは原曲のものをしっかりキャッチしつつ、アレンジをするときは楽譜に頼らず、頭の中で歌う感じです。何度も聴いて、そのイメージを頭の中で反芻しながら、どうピアノに落とし込めるかを考える。で、こんな感じかな?と思ってできたものを、ようやくピアノで弾きます」
――そこで弾いたものは、ほぼ頭でイメージしていた通りなんですか?
「頭の中のイメージを弾いても、実際にはピアノの平均律の状態で鳴るので曖昧な音が出せないことはあります。それをどうニュアンスとしてピアノで表現するかというのは、弾きながら考えるって感じです」
――てっきり譜面を見たり、弾きながら考えるのかと思っていたので意外でした。
「私、曲を書くときも、編曲のときも、ピアノは使わないんですよ。頭の中で鳴っているものを譜面に書いていくのが普段のやり方なんです」
――アレンジをする際、桑原さんがいちばん大切にしていることは何ですか?
「原曲の歌の部分……歌詞があるかないかに関わらず、メロディだったり、メッセージだったりを強く感じる核みたいなところを絶対に壊さないことです。というのも、編曲って曲を変えるのとは違うんですよね。だから私、編曲という言葉を考えた人が、“変”じゃなくて“編”という漢字にしたのは素晴らしいと思います。変奏曲は文字通り曲を変えて奏でるのに対し、編曲は曲を編み直すって感覚。そこはすごく意識していますね。編曲はやっぱり原曲ありきでやらせていただいていることなので、歌詞があるものだったら、それこそ歌詞を譜面に書き起こしますし、その意味を理解してからじゃないと編曲させてもらう権利がないと思っています」
――先ほどの5人の方に選んでいただいた曲以外の選曲はどうされたんですか?
「私が大好きな曲がたくさん入っていますけど、今回は、私が弾いたら絶対に活きると思ってスタッフさんが挙げてくれた曲の中から選んだものが多いです。自分だと勇気が出なくて選べないものもあるので。例えばルーファス・ウィンライトの「ゴーイング・トゥ・ア・タウン」は、アメリカに対するメッセージ性が強い曲なので、日本人の私が弾いていいのかなとか、そういうところも考えてしまうんですよね」
――「ゴーイング・トゥ・ア・タウン」はブッシュ政権下のアメリカについて綴ったプロテストソングですよね。今、世界がこういう状況だからこそ選ばれたのかと思いました。
「そこはスタッフさんが大丈夫だよって言ってくれたので、よし、じゃあ入れようってなりました。自分だったら、おこがましいなと思ってしまうというか。日本だとアーティストが政治のことを口にするのを良しとしない風潮もあったりしますよね。私自身、それにちょっと影響されてしまってなかなか言えないことも。でも、普段は心に押し込めちゃうことが、音楽でなら表現できたり、言葉がないからこそ表現できるものがあったりするのは、ピアノやインストの良さだと思うので。そういうのも汲んだ上で、スタッフさんも大丈夫って言ってくれたんだと思います」
――本作唯一のオリジナル曲「ザ・バック」は、クインシー・ジョーンズに捧げた楽曲だそうですね。
「「ザ・バック」は2016年くらいに書いた曲ですね。その頃、ピアノと格闘しているうちにスランプに入ってしまい、曲が書けなくなっちゃったんですよ。自分の中に、私はこうなりたいっていう理想像がずっとあったんですけど、それに届かない自分がすごくイヤで」
――どんな理想像だったんですか?
「例えば、マイケル・ジャクソンって生活感ないですよね。ステージに立っているときって、マイケル・ジャクソンはマイケル・ジャクソンでしかなくて。そういうアーティスト像が憧れだったんです。だから、人にどう見られるかをすごく気にしていて、生活感のない非日常的なものを提供したいと本気で思っていました。当時は曲の書き方においても人とは違うものにしなければっていう意識が強かったので、3週間ぐらい作曲期間を設けたとしたら、その間は扉とかも全部閉め切って、人にも一切会わず、1人だけの空間でどんどん自分を追い込むのが常だったんです。音楽だけに没頭し、いわゆる“生活”をしていない中で出てくるものこそが芸術なんだ、と。それを21歳でデビューしてから4年ぐらいずっとやっていたら、『Windows』というアルバムを作った直後に曲を書けなくなってしまって。書くのが怖いじゃないですけど、ペンを持つと涙が出てくるみたいな」
――それはずいぶんと苦しい状態ですよね。
「そのスランプが1年半くらい続きました。その終盤、クインシー・ジョーンズが関わっているモントルー・ジャズ・フェスティバルのピアノコンテスト日本代表に選んでいただき、迷いながらも参加することにしたんです。そしたら、私の出番の直前にクインシーが会いに来てくれて、“賞のことは考えずに今のあなたの音を聴かせてください”と声を掛けてくださって。私としては、スランプの真っただ中だったこともあり、賞を獲らないと日本に帰れないと思っていたんです。自分の演奏がどうのとかはまったく考えられず、とにかく間違えないようにしないとって感じだったんですけど、クインシーにそう言われて目が覚めて。直後に出たステージで、本来なら課題曲とオリジナル曲を弾かなきゃいけなかったのを、思い付きで課題曲を即興にしちゃったんです。そしたら、それを聴いてくださっていたクインシーが“今のは即興だったでしょ”って。見抜かれてました(笑)。さらに“即興で弾いたあれが“今”の君の音なんだろうけど、本当にジャズだったし、音楽だった。君に足りないものは何もない”と言ってくれたんです。足りないものは、生きて経験するだけだって。そう言われて、私、クインシーの前でめちゃめちゃ泣いちゃって。クインシーもお父さんみたいにずっと私の肩を撫でてくれて」
――忘れられない特別な出来事ですね。
「本当、あのときクインシーにもらった言葉は私の宝物です。その後、クインシーが帰っていく後ろ姿を見ていたら、またまた涙が出てきてしまって。そのときに、この気持ちを残さなければいけない、残すには曲を書く以外方法がないと思って、日本に帰る飛行機の中で五線紙とペンを取り出して書いた曲が「ザ・バック」です。そして、この曲を書いた後、スランプから抜けたんですよ。それまでの考え方とか理想像が吹っ飛んで、曲の作り方も変わったし、人としてまず日常を生きることを大切にするようになりました。それからは、どんな環境や状況であっても曲が書けるようになったし、ピアノに対しての意識も変わって、音が変わっていくのも早かったです。あの出来事は、間違いなく私のピアノ人生のターニングポイント。「ザ・バック」は私のあらゆるレパートリーの中でも想いが一つ上にあるもので、今回のアルバムにオリジナルを1曲選ぼうってなったとき、「ザ・バック」以外は考えられませんでした」
――曲を書いてから5年、弾き続けている間にこの曲も変化や成長を遂げているんですか?
「私は普段から即興をしているので、基本的に音楽は変化していくものだと思っています。どんな風に形を変えてもいいと思うから、オリジナル曲であってもその日によってグルーヴやアドリブが全然違ったりするんです。でも、不思議なもので、この曲だけはずっと変わらない。ただただ丁寧にテーマを弾き、どの音を何回弾くかもほぼ変わらないんです。あのときの想いのまま、今も変わらずにずっとあるっていう。「ザ・バック」は変える気にならないし、変える必要もないというか。たとえ埃を被ったとしても、そのまま置いておきたいみたいな、そういう存在です」
――どの曲にも桑原さんのこだわりと想いが詰まった今作に『Opera』というタイトルを付けた理由は何ですか?
「レコーディングを東京オペラシティで行ったことと、作品という意味のオーパス(opus)の複数形なので作品がたくさん並んでいるってこと。それから後付けになりますが、私は音楽とは歌だと思っているので、ピアノが歌うという意味も込めています」
――念願のソロ・ピアノ・アルバム、改めてどんな1枚になったと思いますか?
「今しか弾けないものが録れたかなと思います。これが最高峰であるとか、この作品が私の中でマストになるとか、そういう想いは全然なくて。あくまでも通過点として、自分のナチュラルなものが録れたという意味で、とても満足できる1枚になりました」
(おわり)
取材・文/片貝久美子
写真/中村 功
■桑原あいツアー2021 “オペラ, ソロ&トリオ”
2021年6月13日(日) Solo&Trio@ブルーノート東京
2021年6月15日(火) Solo&Trio@BLcafe(愛知)
2021年6月16日(水) Solo&Trio@ビルボードライブ大阪
2021年6月25日(金) Solo Piano@東京オペラシティリサイタルホール

- 桑原あい『Opera』
-
2021年4月7日(水)
UCCJ-2189/3,300円(税込)
ユニバーサルミュージック